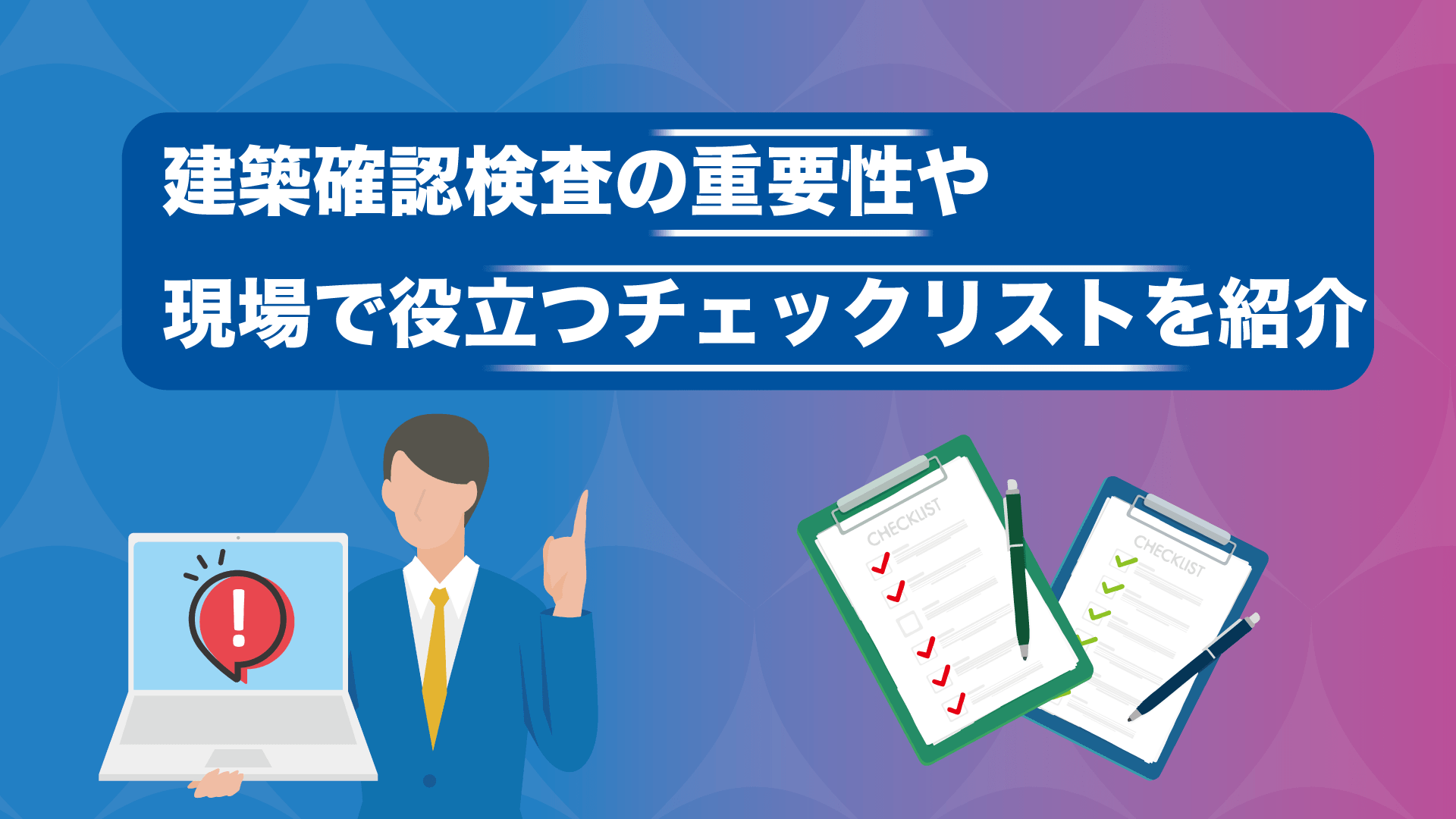施工管理の安全管理とは?業務内容や必須スキルを解説
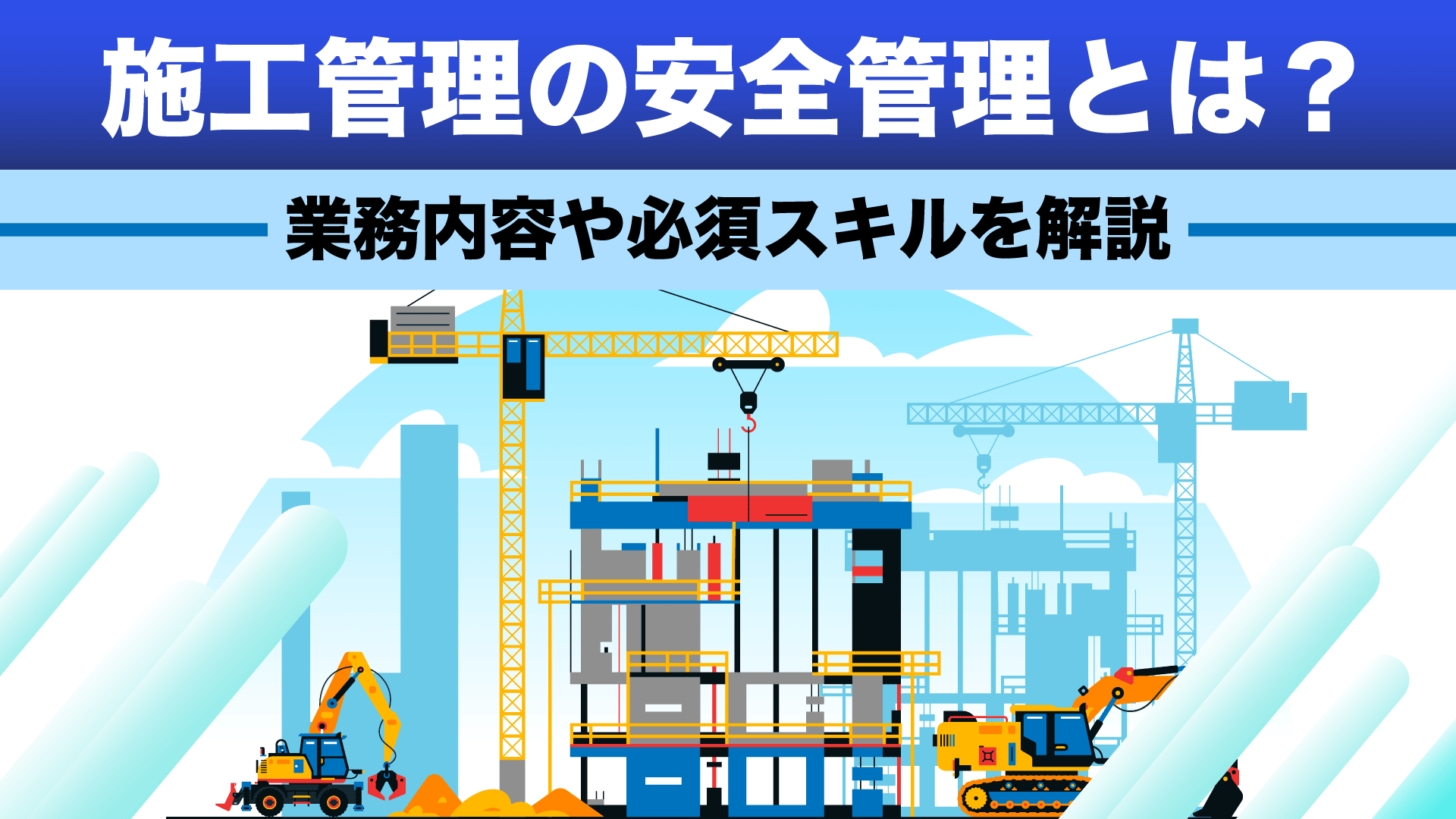
施工管理における安全管理が形だけのものになり、労災リスクの高まりに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
四大管理(工程管理・品質管理・安全管理・原価管理)のなかでも、安全管理は特に優先されるべき業務です。作業員が安心して働ける環境を整え、それを維持することは、現場責任者の重要な責務といえます。
本記事では、施工管理における安全管理の業務内容や重要性、必要とされるスキルや資格、そして現場が抱える課題について徹底解説します。
施工管理における安全管理の重要性
現代の建設業界では、労働災害による死亡事故が全産業の約3割を占める深刻な状況が続いています。あらためて、現場における安全管理の重要性をおさらいしましょう。

作業者の命と健康を守ることが最優先
建設現場は高所作業や重機操作など危険をともなう環境であり、事故のリスクが常に存在しています。そのため、建設現場では、事故を未然に防ぐための取り組みが常時求められます。
厚生労働省の死亡災害統計によると、令和5年における建設業の死亡者数は223人で、前年より58人(20.6%)減少しました。

出典:令和5年 建設業における死亡災害の局別・月別発生状況(確定値)
それでもなお、労働災害による死亡事故は多く、引き続き徹底した安全対策が求められています。
工期や施工品質にも深く関係
安全管理は、工期や施工品質とも深く関わっています。たとえば、現場の安全が確保されていないと、作業が滞りやすくなり、結果として工期に遅れが生じるおそれがあります。
さらに、遅れを取り戻そうとして作業スピードを上げすぎた場合、施工品質が低下する可能性があります。定期的な安全パトロールを通じて、リスクを早期に発見し、対策を講じましょう。
「安全第一」は、最終的にコストや品質の最適化にもつながる、基本でありながら、大切な考え方といえます。
社会的責任と周囲への配慮の必要性
安全管理には、社会的責任や周囲への配慮も欠かせません。騒音や粉じん、交通規制など、工事は近隣住民の生活環境に少なからず影響を与えます。住民の健康や安全に配慮することも、施工管理者に求められる役割です。
そのため、現場周辺の環境や地域の人々への影響を常に意識しながら、安全を確保していく必要があります。安全管理は現場内だけでなく、地域社会との信頼関係を築くための手段です。
施工管理の安全管理に関する基本的なルールと法律
建設業界における安全管理は、労働安全衛生法や建設業法といった法的枠組みによって厳格に規定されています。これらの法律は、建設現場での労働災害を未然に防ぐことを目的に、事業者に対して安全管理の義務を課すものです。
たとえば、労働安全衛生規則第35条では、労働者の雇入れ時に安全衛生教育を行うことが義務づけられており、建設業では原則6時間以上の教育が必要です。
また、建設業法第26条において、一定規模以上の建設工事では主任技術者または監理技術者の配置が義務づけられており、元請事業者には下請業者を含む全作業員の安全確保を統括する責任が課されています。
これへの違反が発覚した場合、事業者には行政処分や刑事罰が科される可能性があり、企業の社会的信用にも大きな影響を与えるでしょう。特に労働災害が発生した際は、損害賠償責任や工期遅延といった経済的な損失が避けられません。

施工管理の安全管理の主な業務内容
安全管理の業務は多岐にわたり、計画段階から実際の作業現場での監視まで、継続的かつ体系的なアプローチが必要です。ここでは、安全管理の主な業務内容についてご紹介します。
- 安全衛生管理の計画立案と体制構築
安全管理の全体設計と役割分担 - 作業員に対する安全教育と意識啓発活動
作業員の意識向上と定着支援 - 作業員の健康状態の把握とヒューマンエラーの予防
体調変化による事故を防止 - 現場設備・工法・作業環境の安全点検
足場や機材の安全性をチェック - 安全パトロールによる現場監視と即時対応
現場の危険を即時に是正 - ヒヤリハット事例(軽微な異常や未然事故)の収集と再発防止対策の共有
未然事例を全体で再発防止
安全衛生管理の計画立案と体制構築
安全衛生管理計画を立案し、安全衛生活動の全体像を具体的に示します。ポイントは、現場ごとに計画書を作成して、誰でも理解できる構成にすることです。ここでは、方針・目標・危険性・重点施策・体制などを記載します。
厚生労働省や自治体も作成を推奨しており、法的な提出義務はないものの、現場運営においては重要な書類といえるでしょう。
作業員に対する安全教育と意識啓発活動
建設業では、労働安全衛生規則第35条に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法的に義務付けられています。さらに、「建設業労働災害防止協会(建災防)」が事業者に代わって実施する「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」(通称:6時間教育)があり、これは原則として6時間の教育を行う任意の制度です。
また、朝礼やKYT(危険予知訓練)を通じて、作業前にリスクを意識させることで、現場全体の安全意識を高められます。災害を未然に防ぐためにも、工程管理とあわせて安全教育を徹底しましょう。

作業員の健康状態の把握とヒューマンエラーの予防
定期健康診断や日々の体調確認を通じて、作業員の健康状態を常に把握します。疲労や体調不良は判断ミスを引き起こしやすく、事故につながるリスクも高まるため、早めの対応が欠かせません。
実際、ヒューマンエラーの多くは健康状態の乱れが原因とされており、未然に防ぐには日常的な健康管理が不可欠です。このような背景から、健康管理は安全配慮義務の一環として明確に位置づけられており、現場管理者にとっても重要な責務のひとつとなっています。
現場設備・工法・作業環境の安全点検
足場・手すりの設置状態や強度を定期的に点検します。使用する機材や機器についても事前に状態を確認し、故障・不具合による事故を未然に防ぎましょう。
あわせて、工法が計画書や図面通りに行われているか、常時チェックします。5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底して作業環境を整えることで、転倒・事故の防止、作業効率の向上につながります。

安全パトロールによる現場監視と即時対応
安全パトロールは、現場の安全確保において欠かせない取り組みです。危険な状態や不備を早期に発見し、即座に是正することで、事故の芽を摘み取ります。また、是正内容を関係者全員に共有し、再発防止につなげましょう。定期的なパトロールの実施により、現場の緊張感と安全意識を維持できます。
安全パトロールについて詳しく知りたい方は、「安全パトロールとは?重要性や現場での確認ポイントを解説」をご覧ください。
ヒヤリハット事例(軽微な異常や未然事故)の収集と再発防止対策の共有
ヒヤリハットとは、事故には至らなかったものの「ヒヤリとした」「ハッとした」ような、軽微な異常・未然事故を指します。これらは、事故につながる危険の芽として、現場で重視されるべき要素です。
「ハインリッヒの法則」では、1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリハットが存在するとされています。実際に報告されたヒヤリハット事例を現場全体で共有し、適切な対策を取りましょう。

施工管理の安全管理に求められるスキル
安全管理には、危機管理能力・コミュニケーション能力・問題解決能力といった3つのスキルが求められます。具体的にどのような影響があるのか、なぜ必要なのかご説明します。
- コミュニケーション能力:作業員同士の情報共有を促進
- 危機管理能力:トラブル時に冷静かつ迅速に対応
- 問題解決能力:トラブルの原因特定と対策立案
コミュニケーション能力:作業員同士の情報共有を促進
現場で安全を守るうえで欠かせないのが、作業員同士のコミュニケーションです。作業中の指示出しはもちろん、何気ない雑談の中からヒヤリハットや体調不良に気づくこともあり、こうしたやりとりが事故の防止につながります。
また、協力会社や他職種との信頼関係を築くことで、現場の雰囲気を良好に保てます。結果、作業員のモチベーションの維持やケアレスミスの抑制が期待できるでしょう。
危機管理能力:トラブル時に冷静かつ迅速に対応
建設現場では、想定外のトラブルが起こることを前提に動かねばなりません。「○○かもしれない」という視点を常に持ち、万が一事故・災害が発生した際には、冷静かつ迅速に対応します。
そのため、日常的な事故事例の確認および分析や、現場経験の積み重ねが不可欠です。日々の教育・訓練が危機管理能力の底上げにつながります。

問題解決能力:トラブルの原因特定と対策立案
危機管理能力と関連しますが、現場では予期せぬトラブルに直面する場面が少なくありません。そうした状況下において、原因を特定し、的確な対応策を講じる力が求められます。たとえば、機器の故障、作業員の欠員、進捗の遅れなどへの柔軟な対応がその一例です。
施工管理の安全管理に必要な資格:「施工管理技士」
建設現場の施工管理を担うには、「施工管理技士」と呼ばれる国家資格が求められます。当該資格は、施工管理者としての専門知識やスキルを客観的に証明するものです。
施工管理技士は担当分野ごとに7種類に分類され、建築・土木・電気・管工事・造園・建設機械・電気通信の各分野に対応しています。それぞれの分野で専門知識が求められるため、現場の特性に応じた技術者の配置が必要です。
資格には1級と2級があり、扱える工事の規模に違いがあります。1級は大規模工事での監理技術者・専任技術者、2級は中規模工事での主任技術者や一般建設業の専任技術者となります。
また、2級の学科試験は実務経験がなくても受験できるため、初心者や若手技術者も取得しやすいでしょう。
また、令和6年度の制度改正により、2級の第一次検定(学科試験)は17歳以上であれば実務経験なしで受験でき、1級の第一次検定も19歳以上であれば実務経験なしで受験できるようになったため、初心者や若手技術者も取得しやすくなりました。第二次検定(実地試験)については、1級・2級ともに実務経験が必要です。
施工管理の安全管理の課題
現代の建設業界では、慢性的な人手不足や情報共有の不備を背景に、従来の安全管理手法では対応しきれない課題が増加しています。その結果、事故リスクの高まりやプロジェクト全体の効率低下といった深刻な影響が懸念されています。
ここでは、建設現場における安全管理上の課題について詳しく解説します。
コミュニケーション不足によるミスやトラブルの誘発
作業員同士の円滑なコミュニケーションは、ヒューマンエラーや事故防止の要です。なかでも最近は、若手の現場監督がベテランの助言に触れる機会が減少しており、現場での判断や対応に不安が残るケースも見られます。
こうした「コミュニケーションの希薄化」は、ミスやトラブルの引き金となり、工期の遅延やコスト増加といったリスクを高めます。
しかし現実には、建設業界全体で慢性的な人手不足が続いており、工事長や主任クラスの技術者が複数の現場を掛け持つ状況が常態化しています。
その影響で現場との対話が十分に行えず、必要な情報が共有されないまま作業が進行するケースも少なくありません。結果、見落としや手戻りといったトラブルが起こりやすくなっているのです。
状況の共有と可視化の不足
墜落・転落といった死亡災害リスクの高い現場では、危険区域や立入禁止エリアの情報を常に共有する必要があります。しかしながら、工事長や主任クラスが複数の現場を抱えており、不安全な行動を把握しきれず、事故発生後に初めて状況を知るケースがあるのです。
また、ヒヤリハットや事故情報は現場で口頭伝達されるだけで終わることが多く、ノウハウとして十分に蓄積されていないのが実情です。たとえ記録が残されていても、テキスト中心では直感的な理解が難しく、安全教育に活用しづらい課題があります。
こうした状況では、情報の共有と可視化が進まず、再発防止や安全管理の質の向上にもつながりにくいのが現場の悩みとなっています。
「SynQ Remote(シンクリモート)」導入で施工管理の安全管理を円滑に!
ここまで見てきたように、施工管理における安全管理では、現場との情報共有やコミュニケーション不足が大きな課題となっています。特に、複数の現場を同時に管理する工事長や主任クラスの技術者にとっては、現地の状況をリアルタイムで把握し、適切な指示を出すことが難しいのが実情です。
こうした課題の解決策になるのが、現場特化型のコミュニケーションツール「SynQ Remote(シンクリモート)」です。
このツールを使えば、管理者と作業員がリアルタイムでつながり、離れた場所からでも現場の確認や指示をスムーズに行えます。専用機器は不要で、普段使っているPCやスマートフォンにアプリを入れるだけで、すぐに導入できるのが魅力です。
図解を使った明確な指示や、現場の“あれ・これ・それ”といった曖昧なやり取りの可視化にも対応しており、コミュニケーションエラーによる手戻りや事故の防止に効果があります。
興味のある方は、ぜひ一度「SynQ Remote」の詳細をご覧ください。現場との情報共有や安全管理の質を高める第一歩として、導入を検討する価値は十分にあります。