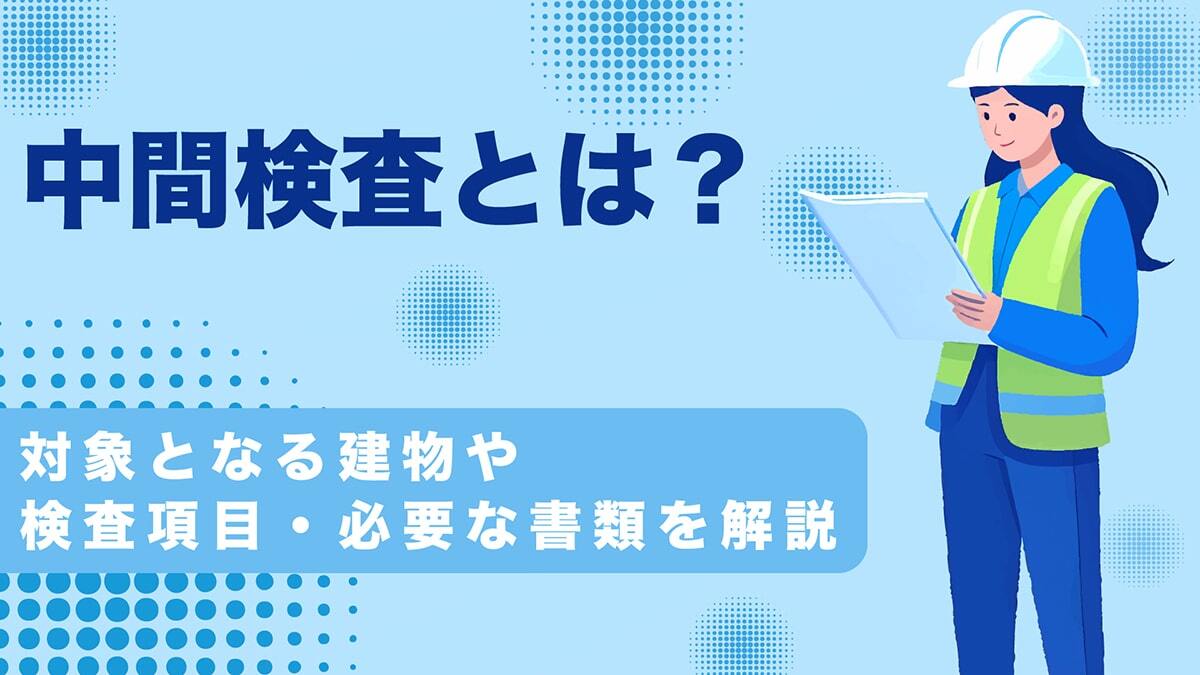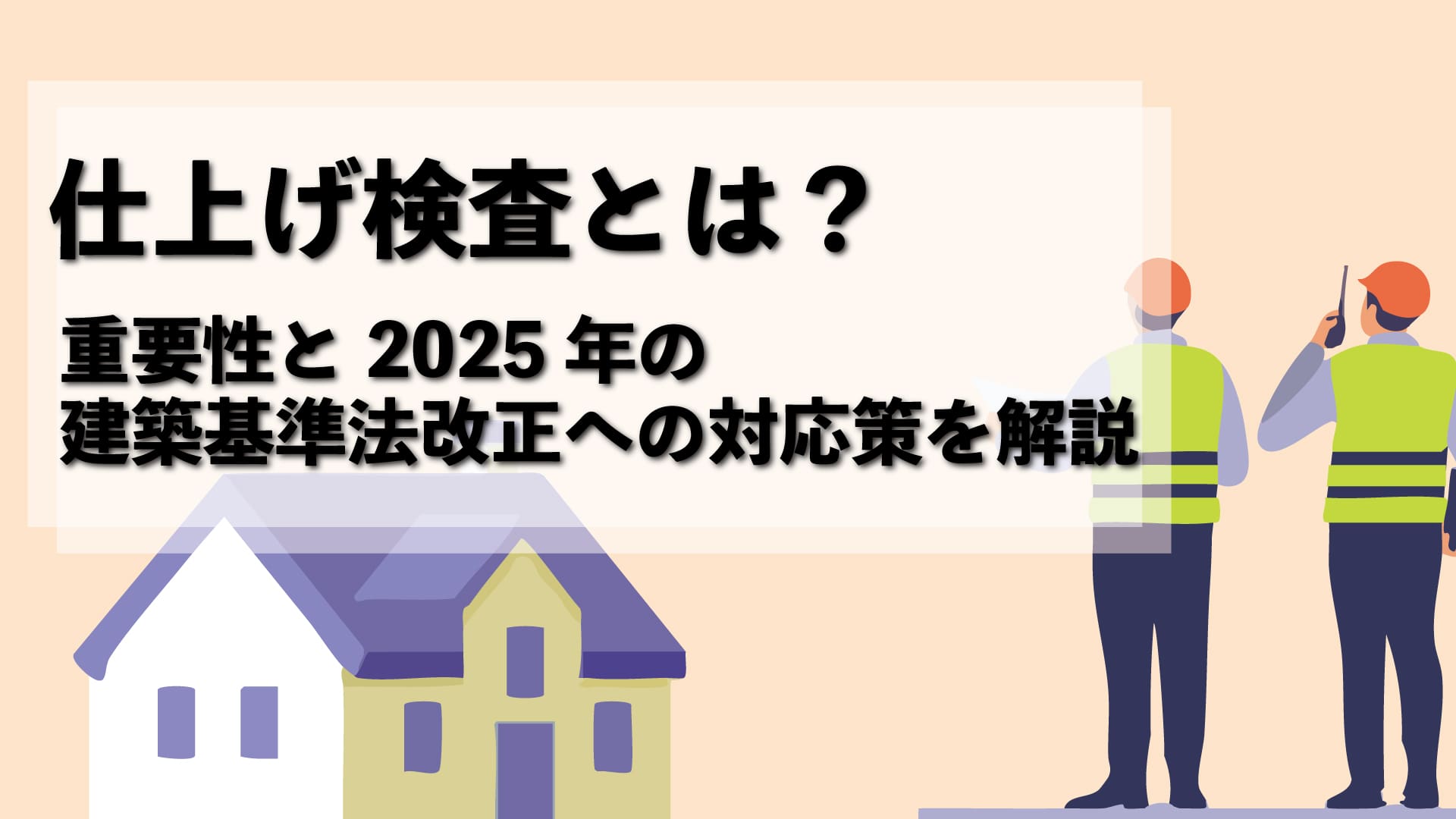【2025年建築法改正】防水・断熱検査の重要性や調査内容を解説
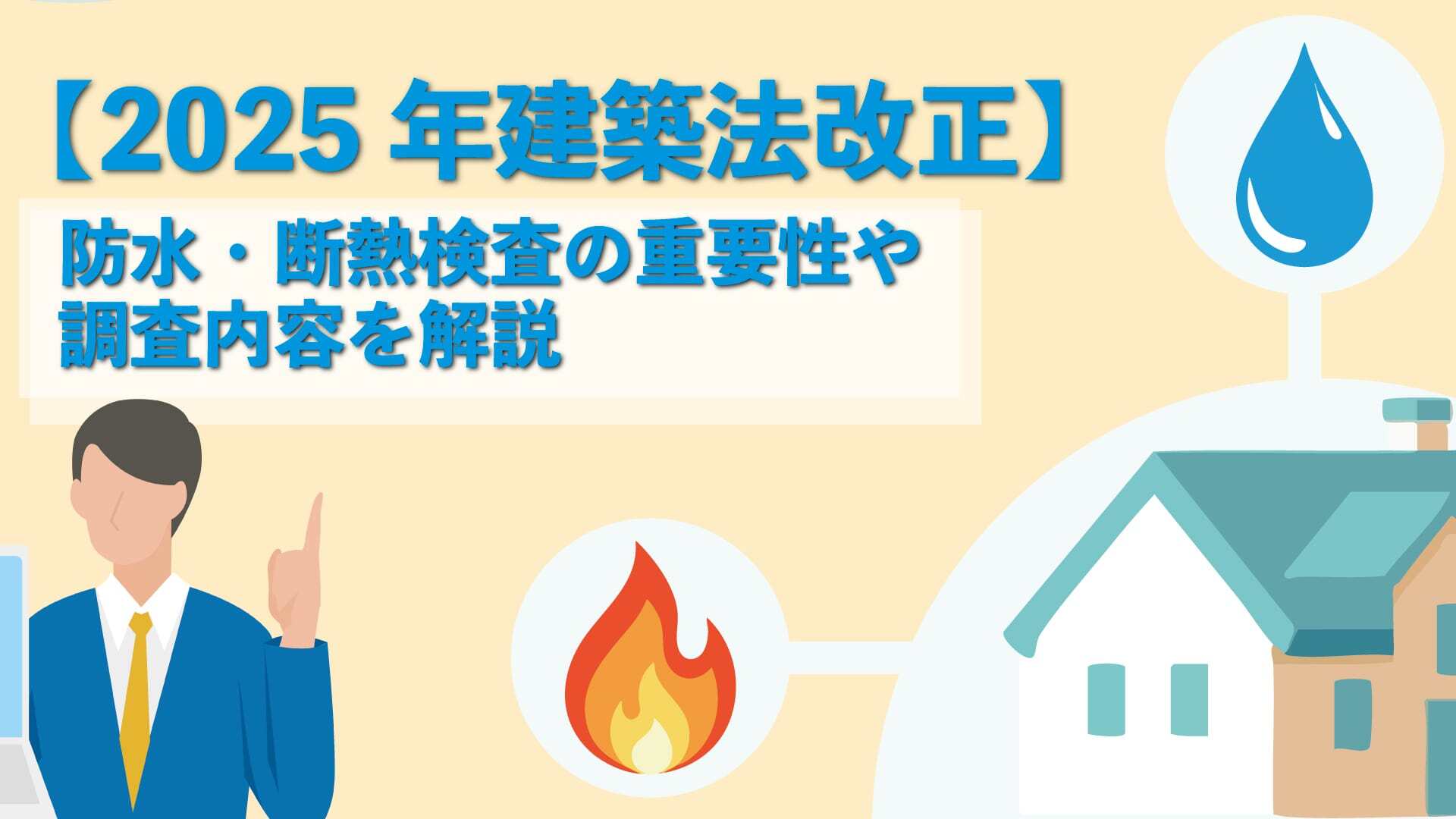
2025年4月の建築物省エネ法改正で、住宅の断熱性能基準が引き上げられました。施工段階では、防水・断熱検査を強化し、完成後に見えなくなる部分を重点的に確認する必要があります。
住宅の品質管理への意識は高まっていますが、検査体制に不安を抱く現場監督も少なくありません。断熱基準が厳格化されたことで、従来のやり方では対応が難しい場面も出てきています。
そうしたリスクを抑えるのが、施工中に実施する防水・断熱検査です。本記事では、法改正のポイントを整理したうえで、防水・断熱検査の実施タイミングや主要なチェック項目、実務で役立つ進め方を解説します。検査体制の見直しを検討している施工管理者の方は、ぜひ参考にしてください。
防水・断熱検査とは?
防水・断熱検査は、建築物の防水層や断熱材の施工状態を確認し、雨漏り・熱損失を未然に防ぐためにおこなう品質確認です。
防水・断熱検査は、内装材で覆われる前に実施します。
防水検査のタイミング
防水検査は、外壁や屋根の防水層施工が完了した段階で実施されます。例えば、透湿防水シートが貼られ、重ね幅やテープ処理が終わったタイミングで、サッシ・配管周りの防水処理も含めて確認します。また、屋根防水層施工後の雨漏り試験を実施することもあります。これにより、建物内部に水が浸入しないことを保証します。
断熱検査のタイミング
断熱検査は、断熱材が施工され、気密処理が施された段階で行います。具体的には、断熱材が設計図通りに隙間なく施工されているか、規定の厚みが確保されているかを確認します。また、通気胴縁が適切に設置され、断熱材が固定されているかもチェックします。このタイミングで施工不良を発見し修正することで、壁内結露や冷暖房効率低下のリスクを防ぎます。
こうした施工段階での検査によって、完成後には目視できなくなる部分の品質を確実に担保できるのです。

また、防水と断熱は工程が近いため、進捗が合えば同時に検査できます。ただし、年度末の3月は引き渡し物件が集中し、検査の見落としやミスが起きやすい点に注意が必要です。中間段階での再検査を取り入れ、施主にも積極的に関与してもらうことが、品質トラブルを防ぐうえで効果的です。
防水・断熱検査の重要性と建築物省エネ法改正による変化
従来は一部の建築物だけが対象だった省エネ基準が、2025年4月からは全面義務化されました。下記のとおり、対象や審査の仕組みは従来に比べて大幅に厳しくなっています。

求められる基準が上がった今、防水・断熱に関する施工不良はそのまま住宅性能の欠陥につながりかねません。小さな隙間や見落としが、快適性の低下や雨漏り・結露といった大きな問題を招くためです。
今一度、防水・断熱検査の重要性と、建築物省エネ法改正による変化および影響についておさらいします。
断熱検査の重要性
断熱材は設計通りに正しく施工されてこそ効果を発揮しますが、施工精度がわずかに乱れるだけで性能は大きく損なわれます。そのため、施工段階での厳格な検査・確認が重要となるわけです。
そもそも断熱材は、設計図通りに隙間なく、規定の厚みで施工されて初めて性能を発揮します。しかし、隙間や欠損があると、その部分が「ヒートブリッジ(熱橋:周囲よりも熱が伝わりやすい部分)」となり、熱の出入り口となります。これにより冷暖房効率が下がるだけでなく、壁内結露を招く可能性があります。
壁内結露は、温度差で壁内部に水滴が発生し、カビや木材の腐食、シロアリ被害の原因になります。一度起きると補修が難しいため、内装工事前に検査を徹底することが欠かせません。

防水検査の重要性
防水検査の目的は、深刻な不具合の一つである雨漏りを防ぐことです。雨漏りは屋根から水が滴るような分かりやすいものだけでなく、壁内部やバルコニーなどで、気づかれないまま進行するケースが少なくありません。
雨水が構造躯体に浸入すると、木材の腐食や鉄骨の錆を引き起こし、建物の強度を大きく低下させます。実際、阪神・淡路大震災に関する調査では、腐朽やシロアリ被害を抱えた住宅の倒壊率が高かったと報告されています。
また、住宅品質確保促進法(品確法)では新築住宅の雨漏りが10年間保証されますが、保証期間を過ぎてから被害が表面化する事例もあります。その際の補修費用は数百万円を超えることもあり、所有者の大きな負担となります。

こうしたリスクを回避し、建物の資産価値と安全性を守るためにも、施工段階での防水検査が欠かせません。
参考文献:京都大学木質科学研究所「阪神大震災にみる住宅の腐朽およびシロアリ被害」
建築物省エネ法改正のポイント
そもそも今回の法改正は、2050年の「カーボンニュートラル実現」という国家目標を背景におこなわれたものです。住宅分野におけるエネルギー消費削減を実現するため、従来は一部の建築物に限られていた省エネ基準が、すべての新築住宅に適用されるようになりました。
特筆すべきは、断熱等性能等級の基準引き上げです。等級は1から7までありますが、かつて最高ランクだった等級4が、今回の改正で「最低条件」となりました。
基準引き上げにより、居住者は光熱費の削減や快適性向上といった恩恵を受けられます。一方で、施工精度がわずかに乱れるだけで、断熱性能が設計通りに発揮されなくなる課題も浮き彫りになりました。
こうした状況を踏まえ、設計者や施工者には確実な知識と技術の習得が求められます。加えて、第三者による検査やチェック体制を整え、施工不良を未然に防ぐ仕組みも必要です。基準を満たせなければ、建築確認済証や検査済証が交付されず、使用開始に支障をきたします。
防水・断熱検査の確認リスト
断熱材や防水シートは完成後に目視できないため、施工段階での検査が住宅性能を左右します。ここでは、防水・断熱検査における確認リストを見ていきます。
断熱検査の確認リスト
断熱検査は、断熱材が設計通りに施工されているかを確認し、熱損失や結露を未然に防ぐために欠かせません。
以下のチェックシートを用いて、主要な確認項目を一つずつ点検していきましょう。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 材料の確認 | 設計図書通りの断熱材(例:グラスウール、硬質ウレタンフォーム等)が使われているか現物と照合 |
| 厚み | 全域で設計通りの厚みが確保されているか実測 |
| 充填状態 | 壁・天井の隅々まで隙間なく施工されているか(配管周りも重点確認) |
| 接合部 | 壁・天井・床、サッシ周りの断熱材が連続しているか |
| 防湿層 | 防湿シートの重ね幅・留め間隔・破損の有無を確認 |
| 結露防止 | 通気層が適切に機能しているか、防湿施工が確実か |
| 固定状態 | 自重や振動でずり落ちないよう固定されているか |
| 完了後検証 | サーモカメラや気密測定で隙間を確認 |
防水検査の確認リスト
防水検査は、構造体を守るための生命線です。雨漏りは室内への浸入にとどまらず、木材の腐食や鉄骨の錆を招き、耐震性を著しく低下させます。
以下に、施工段階で押さえるべき主要なチェック項目をまとめました。
| 確認項目 | 詳細なチェック内容と重要性 |
|---|---|
| 防水層の施工状態 | バルコニーや陸屋根で、防水層(ウレタン塗膜・FRPなど)が設計通りに施工されているか確認。塗膜は規定厚(例:2mm以上)が必要で、ひび割れやピンホールも要点検 |
| 防水シートの施工 | 外壁の透湿防水シートが、重ね幅や開口部処理を含めてマニュアル通りか確認。サッシ周りや配管部は漏水リスクが高いため重点チェック |
| 排水処理 | バルコニーや陸屋根に適切な勾配(1/50以上)があるか、排水口の位置や口径が適切か確認。ストレーナー設置も必須 |
| 立ち上がり部分 | 防水層が壁際に規定高さ(サッシ下150mm以上など)までしっかり巻き上げられているかを確認。雨漏りの多発部位 |
| バルコニー・陸屋根の仕上げ | 防水層の浮きや剥がれ、トップコートの均一性を点検。特に排水溝周辺や手すり根元など複雑部位を重点確認 |
| 屋根防水 | 屋根材下のルーフィングが破損なく、規定の重ね幅(100mm以上)を保っているか。谷部や棟部での部材設置も確認 |
| 補修箇所 | 施工中のシート破れや不具合の補修が適切におこなわれ、一体化しているかをチェック。補修不良は弱点化の原因に |
| 窓・開口部周辺 | サッシや玄関ドア周りで、防水テープが正しい順序(下→左右→上)で貼られているか、シーリング材が隙間なく充填されているか確認 |
| 施工後の確認試験 | 水張り試験(一定時間水を張って漏水を確認)、散水試験(外壁に散水して浸入を確認)で、防水性能を実証 |
断熱・防水検査を効率よく進めるポイント
断熱・防水工事の品質を守りながら検査を効率化するには、仕組みづくりが欠かせません。チェックリストで確認漏れを防ぎ、スタッフ教育で施工精度を高めましょう。
さらに、ウェアラブルカメラなどの遠隔技術を使えば、専門家が現場をリアルタイムで確認でき、検査の効率と精度を両立できます。以下、断熱・防水検査を効率よく進めるポイントを解説します。断熱・防水検査は以下の4つのポイントを意識すると効率よく進めることができます。
確認リスト(チェックリスト)の活用
現場での断熱・防水検査を確実かつ効率的に進めるには、専用のチェックリストが欠かせません。人の手による作業ではヒューマンエラーを避けられないため、複数担当者によるダブルチェック体制を整えることが大切です。
先にまとめたリストを活用し、断熱材の種類や厚み、隙間の有無といった基本項目に加え、防湿シートの施工状況や開口部の防水処理など、専門的な内容も体系的に確認しましょう。これにより、検査員の経験差に左右されず、常に一定水準の品質を確保できます。

教育とトレーニング
設計通りの性能を実現するためには、施工スタッフの技術力向上が重要です。自社のスタッフに断熱・防水工事の重要性を改めて教育し、最新の施工基準や工法に基づいたトレーニングをおこないましょう。
具体的には、赤外線サーモグラフィを用いた断熱欠損の確認や、水張り試験による防水層の検証など、専門機器を正しく扱う実践的な技術指導が効果的です。
クレーム防止への取り組み
完成後は壁や天井の内部が見えなくなるため、不具合が隠れやすく、表面化したときには構造体の腐食やカビの発生など被害が広がっているケースもあります。その結果、補修費用が高額となり、顧客との信頼関係を損なう要因になりかねません。
こうしたリスクを避けるには、施工品質を客観的に示せる仕組みが必要です。たとえば、施工完了後に第三者機関の検査結果報告書を写真付きで提出すれば、顧客は専門的な内容を視覚的に理解でき、安心感を得られます。
加えて、防水施工については保証期間を契約書に明記し、長期的なアフターサービス体制を整えることが、企業の信頼性を高め、顧客満足度の向上にもつながります。
最新技術の導入と遠隔検査の活用
建設業界の人手不足や働き方改革に対応しながら施工品質を高めるには、最新技術の導入が効果的です。たとえば、AIやIoTによる監視システムを使えば、建物完成後も温湿度を遠隔で継続的にモニタリングでき、異常を早期に発見できるでしょう。
検査工程の効率化では、ウェアラブルカメラを活用した遠隔臨場システムの導入が有効です。作業員が装着したカメラを通じて、遠隔地の技術者や設計者が現場をリアルタイムに確認できるため、移動せずに複数現場を同時にチェックでき、時間とコストの削減につながります。
さらに録画データを保存すれば、施工のトレーサビリティを確保し、原因究明や若手技術者の教育にも役立ちます。こうした遠隔技術は、検査の頻度と精度を高め、人為的ミスを減らすうえで重宝します。
そこで役立つのが、遠隔臨場に特化した「SynQ Remote(シンクリモート)」です。ウェアラブルカメラなどの機材を必要とせず、スマホやタブレットで現場と事務所をリアルタイムでつなぐことができ、効率と精度を両立する検査体制を可能にします。

(シンクリモート)」導入で防水・断熱検査をもっとスムーズに!
「SynQ Remote(シンクリモート)」は、遠隔支援に特化したツールで、高精細な映像共有、ポインター機能、撮影・書き込みなどに加え、AI議事録機能を備えています。これにより、現場での会話や指示内容を自動で文字起こし・要約し、そのまま報告書形式に整理できます。
この機能を活用すれば、防水・断熱検査で得られたチェック結果や補足コメントを即座に文書化でき、従来は検査後に時間をかけてまとめていた記録整理や是正指示作成の手間を大幅に削減できます。時間短縮と記録精度の向上を同時に実現できるのが特長です。
さらに、録画データやAI議事録で生成された報告書はクラウドに保存され、後日の見返し・原因究明・技術者教育にも活用可能です。防水・断熱検査における「記録の抜け・見落とし」や「報告作成の遅延」といった課題を解決するための、有効な手段となります。
検査体制の改善を検討されている方は、ぜひ「SynQ Remote」のAI議事録機能を含む各種機能をご確認ください。