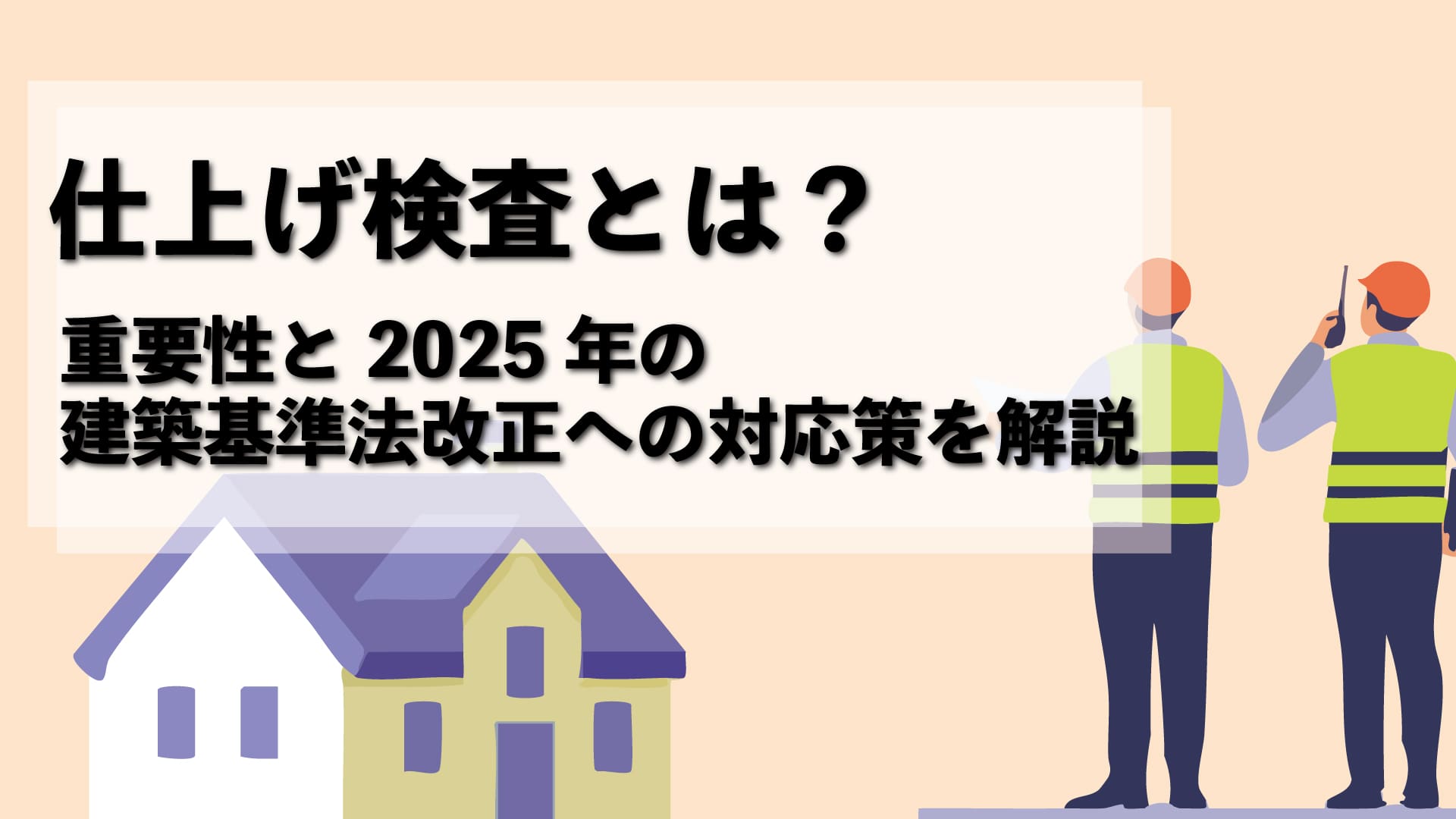【建築基準法改正】基礎工事検査のチェックポイントやタイミングを解説

品質管理やコンプライアンスへの意識が高まる中、自社の基礎工事検査体制に不安を感じている現場監督の方も多いのではないでしょうか。特に、2025年に施行された建築基準法の改正によって、検査要件がより厳格になり、従来のやり方では対応が難しい場面も出てきています。
本記事では、改正建築基準法を踏まえた基礎工事検査の実施タイミングや、押さえておきたい主なチェックポイント、現場で注意すべき事項を実務目線で解説します。
検査体制の見直しやチェックリストの整備を検討している施工管理者の方は、ぜひ参考にしてください。
基礎工事検査とは?
基礎工事検査は、建物の土台となる基礎部分が設計図書や各種基準に則した正しく施工されているかを確認する工程です。建物の構造強度、安全性、そして耐久性を保証するうえで欠かせません。
ここからは、基礎工事検査の基本的な内容と、その重要性について詳しくご紹介します。

基礎工事検査の重要性
建物の基礎は、全体の重量を支え、その荷重を地盤へ均等に伝える役割を担っています。そのため、基礎工事の品質は構造全体の安全性に直結するといえるでしょう。
検査によって設計通りの強度が確保されているかを確認することで、不同沈下や構造体のひび割れといった将来的なトラブルを未然に防げます。
法的遵守とトラブル防止
建築工事では、建築基準法にもとづき、特定の工程において第三者機関による検査が義務付けられています。なかでも基礎工事検査は、住宅や商業施設を問わず、構造の安全性に直結する重要な項目であり、地域によっては条例により中間検査の対象とされる場合もあります。
中間検査については「中間検査とは?対象となる建物や検査項目・必要な書類を解説」をご覧ください。
資産価値の維持向上
どれほど魅力的な建物でも、基礎に問題があれば長期的な価値は保てません。目に見えない部分なので、施工段階での厳密なチェックが必要なのです。
たとえば、配筋の誤りや型枠の不備などは、完成後では発見が難しく対応にも多くの手間と費用がかかります。だからこそ、工事中に不具合を早期に見つけ、適切な処置を施すことが大切です。
こうした対応が、将来的な修繕リスクを軽減し、資産価値の下落を防ぐことにつながります。
基礎工事検査(配筋検査)のタイミング
基礎工事における重要な工程のひとつが、コンクリート打設前に実施する配筋検査です。コンクリートが硬化してしまうと、内部の鉄筋を目視で確認したり修正したりするのは非常に難しくなるため、鉄筋をすべて組み上げたあと、型枠にコンクリートを流し込む直前のタイミングで検査をおこないます。

基礎工事検査(配筋検査)の手順
配筋検査では、検査員が現場で基礎伏図や断面図、仕様書などの設計図書と照らし合わせながら、実際に組まれた鉄筋の状態を確認します。
また、鉄筋を錆から守り、コンクリートとの付着を確保するために必要な「かぶり厚さ」については、規定どおりの寸法が確保されているかを丁寧にチェックします。
加えて、土台と基礎を緊結するアンカーボルト、地震時に柱が土台から抜けるのを防ぐホールダウン金物についても、位置や本数、固定状況などを厳格に確認する決まりです。
「2025年建築基準法改正」における基礎工事検査への影響
2025年4月1日に施行された建築基準法の改正は、建物の安全性を一層強化するため、とりわけ小規模建築物の確認申請手続きに影響を与えています。
ここからは、建築基準法改正が基礎工事検査に与える影響をはじめ、「4号特例」の見直しや審査体制の変化について解説します。
【比較表】建築基準法改正による基礎工事関連の変更点
今回の法改正で、特に木造2階建て住宅などがどのように変わったのかを、改正前後の比較表にまとめました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 建築物の区分 | 4号建築物(木造2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下など) | 新2号建築物(木造2階建て、または木造平屋建てで延べ面積200㎡超) |
| 建築確認時の審査 | 構造関係規定の審査は省略(4号特例) | 構造関係規定への適合性審査が必須 |
| 基礎に関する審査 | 図面提出が免除されるため、実質的に審査は行われない | 基礎伏図や仕様書等にもとづき、構造安全性を厳密に審査 |
| 主な提出書類 | 付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図など | 構造計算書または構造安全性を明記した仕様書、基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図など |
| 審査の主眼 |
主に面積や高さなどの形式的要件 |
省エネ性能や構造安全性などの性能要件 |
| 設計・工事への影響 | 設計者の裁量に委ねられる部分が大きかった | 法的基準にもとづいた明確な構造設計と、それを証明する書類作成が欠かせないとなり、現場での検査も厳格化される |
※都市計画区域外の新3号建築物については、これまで通り確認審査が省略されるケースもあります
※該当の判断は、各自治体が定める告示や要綱によって異なるため、事前の確認が必要です
この表をもとに、特筆すべき以下の点を掘り下げていきます。
- 検査対象の拡大と実施の厳格化:4号特例の見直し
- 検査プロセスの厳格化:構造・省エネ性能の適合確認が拡大
- 必要書類の増加と審査体制の変化:安全性を証明する詳細な図書を提出
検査対象の拡大と実施の厳格化
今回の法改正で注目すべきは、4号特例の見直しです。これまで、木造2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の小規模な建築物(通称:4号建築物)については、建築確認申請時の構造関係規定の審査が省略されていました。
しかし、2025年4月1日以降に着工する建築物からは、この特例の対象が「平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の木造建築物」などに限定され、新たに「新3号建築物」として定義されました。これにより、従来4号建築物に該当していた多くの木造2階建て住宅などは、「新2号建築物」という新たな区分へ移行することになります。
新2号建築物では、建築確認申請の際に構造安全性の証明が求められ、確認検査機関による構造審査が義務化されました。これにともない、基礎工事に対する検査体制も実質的に強化されたといえるでしょう。
検査プロセスの厳格化
既存建築物の老朽化や耐震性の問題が表面化する中、4号特例の見直しによって、確認申請および審査における構造・省エネ性能の適合確認が拡大されました。従来の目視中心のチェックに加え、提出された図書との整合性を確認するなど、より詳細な検査へと移行しています。
また、これまでは、建築物の規模・構造に応じて確認審査が簡略化されるケースもありましたが、今後は提出書類の精度や整合性までが審査対象となります。配筋検査においても、構造計算書との整合性を確認する工程が新たに加わり、検査の内容が一層厳密になりました。

必要書類の増加と審査体制の変化
新2号建築物に該当する場合は、従来の基本的な図面に加えて、構造安全性を証明するための詳細な図書を提出しなければなりません。
具体的には、構造計算によって安全性を確認する計画である場合、「基礎伏図」「各階床伏図」「小屋伏図」といった構造図に加え、構造計算書の提出が必要です。
さらに、確認検査機関の審査体制も見直されました。これまでは、延べ面積や建物の高さといった形式的な要件を中心に確認していましたが、今後は建物の省エネ性能や構造安全性といった「性能要件」そのものが、審査の中心となります。
改正後の基礎工事検査の主なチェックポイント
ここでは、建物の耐久性と構造安全性に深く関わる主要なチェックポイントを、以下5つのポイントにわけてご紹介します。

- 鉄筋の配置(配筋検査)の確認|図面と一致しているかを確認
- 材料・試験データの確認|品質証明書・試験結果で仕様をチェック
- 地盤・基礎仕様の適合性確認|地盤条件に合った基礎形式か確認
- 工程写真・全体記録の整備|検査の証拠となる記録を残す
- 中間検査書類(チェックシート)の提出|監理記録をまとめて保管
鉄筋の配置(配筋検査)の確認
鉄筋の網目幅が図面どおりであるかを細かくチェックします。具体的には、コンベックスなどの測定器具を使って網目の間隔を実測し、鉄筋の交差部分が一定間隔で針金によりしっかりと結束されているかを目視で確認します。
この結束が不十分な状態だと、コンクリートを打設する際の圧力によって鉄筋がずれ、設計された強度が確保できなくなるおそれがあります。
材料・試験データの確認
使用される資材が設計図書で指定された規格に適合しているかどうかを、各種書類や試験結果をもとに確認します。具体的には、コンクリート強度試験のデータ、鉄筋のミルシート、セメントや骨材に関する品質証明書などです。
なかでも、コンクリートの強度は基礎の耐久性に直結する要素です。現場で実際に使用するコンクリートから採取したサンプルを用いて圧縮強度試験を実施し、その結果が記載された報告書を漏れなく確認しましょう。
地盤・基礎仕様の適合性確認
基礎の形式が、地盤の許容支持力や沈下特性に対して適切であるかを事前に確認します。設計にもとづいて基礎形式が選定されているか、地盤の性質と整合しているかを、調査結果などから判断しましょう。
また、地盤改良を実施した現場では、設計図書に記載された範囲や深さ、使用材料に誤りがないかを確認してください。改良後に求められる強度が得られているかどうかを、記録や試験データをもとに検証します。
工程写真・全体記録の整備
配筋の配置や型枠の設置、コンクリートの打設といった作業は、完了後に視認できなくなるため、工程ごとに写真を撮影・記録することが重要です。これにより、検査時や万一のトラブル発生時にも、施工内容を客観的に証明できます。
また、撮影した記録は、現場監督や設計者などの関係者とリアルタイムで共有できる体制を整えておくと、情報の伝達や判断がスムーズになり、全体の品質管理にもつながります。

中間検査書類(チェックシート)の提出
中間検査書類は、基礎工事が設計図書に基づいて正しく施工されたことを証明するための重要な書類です。提出の際は、記載内容に不備がないかを確認し、添付すべき書類がすべて揃っているかを丁寧にチェックする必要があります。
あわせて、工事監理の経過を示す品質管理記録も提出対象となります。たとえば、配筋検査の確認結果やコンクリート強度試験のデータなど、各工程で記録された情報が整理され、相互に矛盾がない状態で提出されていなければなりません。
改正後の基礎工事検査の注意点
改正後の配筋検査では、設計図書との整合性を厳密に確認するだけでなく、検査内容を詳細に記録し、関係者間で情報を共有する仕組みの構築が重要となりました。
検査の透明性を高め、記録の信頼性を確保することが、これまで以上に重視されています。ここでは、実務上注意すべき3つのポイントについて、項目別に解説します。
- 最新図面・仕様書を使用する:最新版を必ず確認
- 配筋検査では図面と照らし合わせて写真を撮る:整合性が一目でわかる構図に
- 検査写真を共有する:全関係者でリアルタイムに情報を共有・確認
最新図面・仕様書を使用する
法改正や設計変更があったにもかかわらず、古い図面・仕様書を使用すると、最新の基準に適合しない可能性があります。特に構造計算や地盤調査結果の更新があったときは、基礎の配筋仕様や寸法に変更が生じる場合があるため、検査前には必ず最新版の設計図書をチェックしてください。
配筋検査では図面と照らし合わせて写真を撮る
改正後は記録の重要性が増し、より詳細な記録が求められています。検査写真撮影時には、設計図面を現場に携行し、図面に記載された配筋仕様と実際の施工状況の対比がわかる構図を意識しなければなりません。
検査写真を共有する
検査写真は建築主、設計者、施工者、検査機関など、複数の関係者間で共有する必要があります。一方、従来のように紙ベースの報告書を用いた運用では、情報伝達に時間がかかり、関係者間で認識にずれが生じるケースも少なくありませんでした。
こうした課題に対応するため、国土交通省はクラウドサービスや専用アプリといったデジタル技術の活用を推進しており、実務においても情報共有の円滑化に向けた活用が期待されています。
「SynQ Remote」で検査写真の即時共有・保存が可能!
2025年の建築基準法改正により、基礎工事検査の範囲は拡大され、検査内容もより厳格になりました。これにあわせて、配筋状況の記録や検査写真の管理、関係者間での情報共有など、現場の対応レベルも一段と高まっています。
なかでも、検査写真のリアルタイム共有は非常に重要です。建築主・設計者・施工者・検査機関の全関係者が同時に内容を確認できる体制を整えることで、検査の透明性と信頼性が大きく向上します。
しかし、実際にはスケジュール調整や現場への移動に時間やコストがかかり、検査プロセスの効率化に課題を感じている施工管理者は少なくありません。
そこでおすすめなのが、現場業務に特化したビデオ通話ツール「SynQ Remote(シンクリモート)」です。
「SynQ Remote」を活用すれば、現場の状況を遠隔で確認できるため、検査立ち会いのための移動が不要になります。また、検査写真のリアルタイム共有や保存も可能で、改正後の検査要件に対応した効率的な運用を実現できます。
現場の負担を軽減しながら、検査の質とスピードを両立させたい方は、ぜひ「SynQ Remote」の導入をご検討ください。