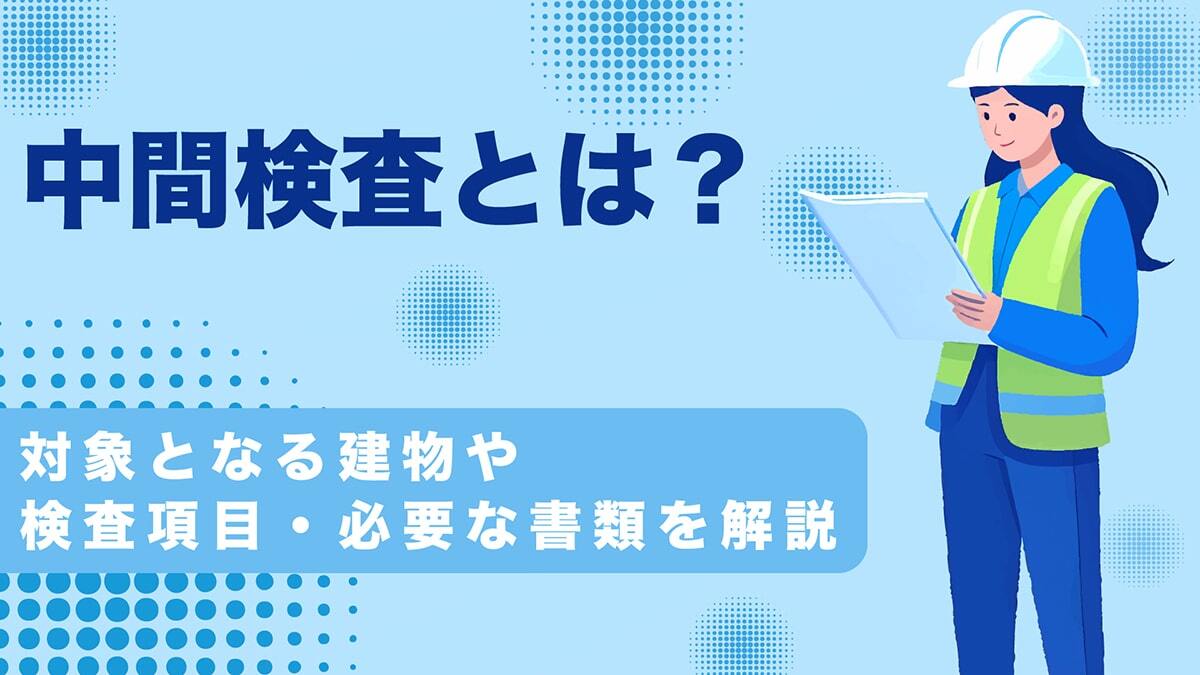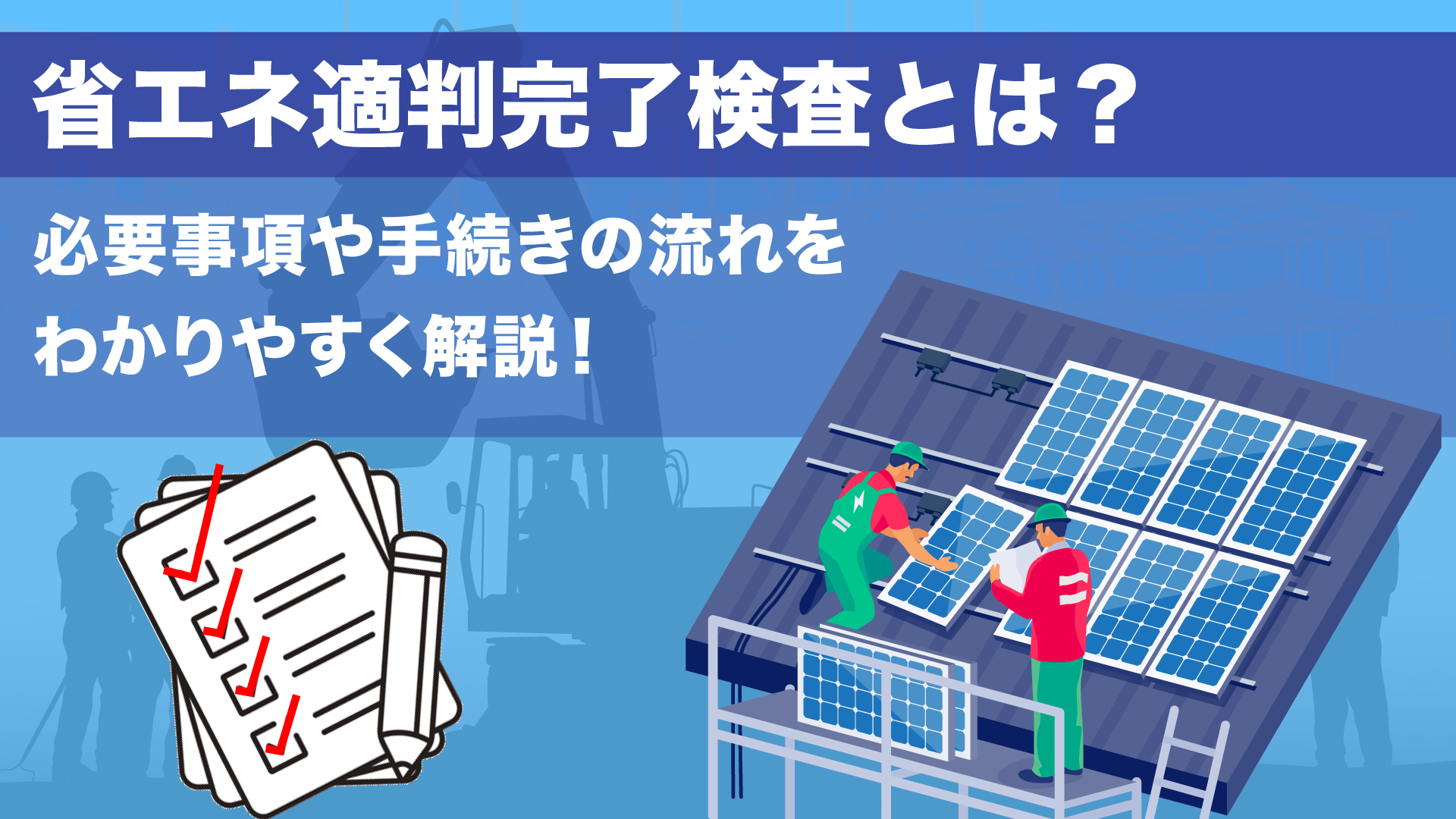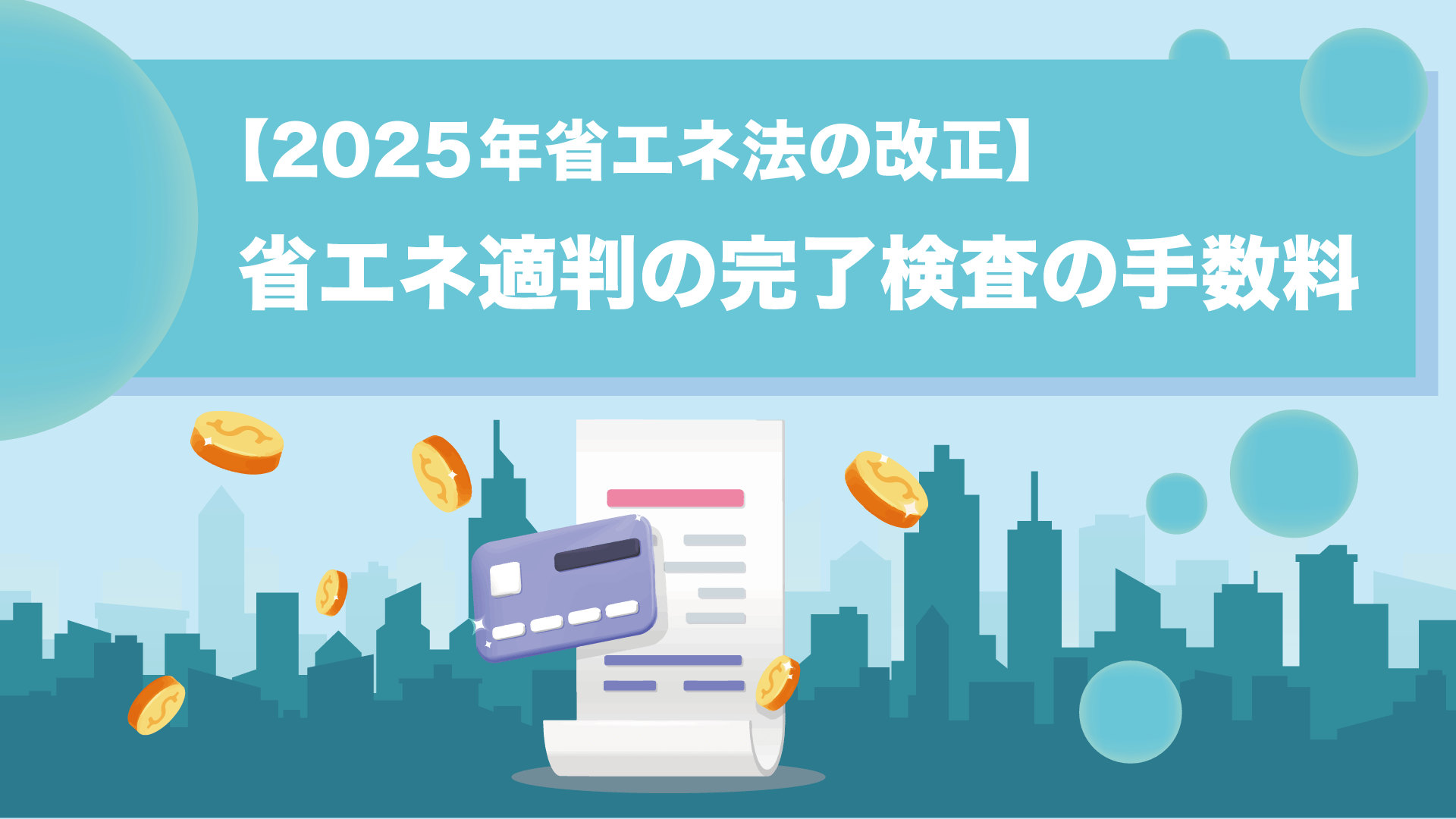建築の完了検査とは?必要書類や注意点・法改正による影響を解説

建築基準法や省エネ法の改正によって、「どの書類を準備すればよいのか」「申請や検査対応に漏れがないか不安」といった声が現場から聞かれる事が増えています。実際、改正内容を十分に理解できず、検査員から指摘を受け、追加手続きに追われるケースも増えています。
本記事では、建築の完了検査に不安を抱える方に向けて、効率的に進めるためのポイントをわかりやすく解説します。
建築物の完了検査とは?
完了検査は、建築基準法第7条第1項で義務付けられている手続きで、新築工事や大規模なリフォームが終わった建物が適法に施工されているかを確認するものです。検査に合格すると「検査済証」が発行されます。
「検査済証」は、建物が建築基準法に適合していることを公的に証明する書類であり、建物の安全性や適法性を保証する役割があります。交付されなければ、原則としてその建物を使用することはできません。
将来的に建物を売却・増改築を行ったりする際にも、検査済証が必要です。適法性を証明し、資産価値を守るうえで重要な書類です。
完了検査の内容:工事完了日から4日以内に提出
建築主は工事が完了した日から4日以内に完了検査を申請する義務があります。申請を受けた検査員は、7日以内に現場検査を行うことが法律で定められています。
完了検査の目的は、建築確認申請時に提出した設計図書どおりに施工されているかを確認することです。建物本体だけでなく、電気・ガス・上下水道などの設備、外構や敷地の状況、周辺道路との取り合いなど多岐にわたります。専門の検査員が建築基準法や関連法令に基づき、細かくチェックします。

完了検査の検査員(各自治体・指定確認検査機関)
完了検査の検査員は、検査を依頼する機関によって異なります。通常、都道府県・市に検査を依頼した場合は「建築主事」が、民間の指定確認検査機関であれば「確認検査員」が担当します。
現在、完了検査の実施件数の約9割は、民間の指定確認検査機関が対応しています。これは、自治体のみでは検査件数に対応しきれない現状と、民間機関の方が予約を取りやすいためと考えられています。
また、建築主事および確認検査員は、完了検査だけを担当するわけではありません。たとえば、着工前に提出される書類・図面が法令に適合しているかを確認する「建築確認」、特殊な構造や規模の建物で施工中に行われる「中間検査」も、各役職の仕事です。
中間検査について詳しくは「中間検査とは?対象となる建物や検査項目・必要な書類を解説」をご覧ください。
建築基準法・省エネ法改正の影響
2025年4月1日に改正された建築基準法では、建築物の安全性や環境性能を一段と高める変更が盛り込まれています。
本改正により、これまで適用されていた「4号特例」が大幅に縮小され、さらにすべての新築建築物に省エネ基準の適合が義務化されるなど、完了検査の運用にも大きな影響が出ています。
以下は、改正前後の主な違いをまとめた比較表です。

参考:国土交通省「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」
注目すべき変更は、「新3号建築物」として審査省略が認められる範囲が大幅に限定された点です。改正後、省略対象となるのは、木造平屋建てかつ延べ面積200平方メートル以下の建築物のみとなりました。
その結果、これまで省略対象だった木造2階建てなどは新たに確認申請時の審査が必要となり、完了検査においてもより厳密な確認が行われるようになります。
完了検査の必要性・行わないリスク
完了検査は、建築物が安全であり、かつ建築基準法などの法令に適合して施工されたことを証明するための手続きです。もし完了検査を怠った場合、建物が法的に適合していると認められず、資産価値や信頼性が大きく損なわれるリスクがあります。詳しく見ていきましょう。
検査済証を交付されない:住宅ローン・増築が不可
多くの金融機関では、住宅ローンや不動産担保融資を利用する際に検査済証の提示が必須です。検査済証がない建物は、法的な適合性が確認できないため、融資の対象外となり、売買時には現金一括取引が求められる場合が多くなります。その結果、市場価値が下がり、安い価格でしか売却できなくなる可能性があります。
また、将来的に大規模な増改築を検討する際にも検査済証が必要です。特に防火地域や準防火地域では、検査済証がないと増築の許可が下りず、建物の活用方法が大きく制限されます。

違反建築物と認定される:罰金・懲役・免許取り消しの可能性
完了検査を受けずに引き渡した場合、その建物が違反建築物として認定される可能性があります。
違反建築物と判断されると、発注者である建築主には懲役や罰金が科されるほか、施工に関わった工務店や建築会社も免許取り消しや業務停止などの行政処分を受ける恐れがあります。
事実、建築基準法第99条には、中間検査や完了検査の申請を怠った建築主に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す規定が明記されています。
このような処分は建築主個人だけでなく、施工業者や設計者など、関係者全員に深刻な影響をおよぼすため、完了検査を確実に受けなければなりません。

完了検査の必要書類
完了検査を申請する際には、建築基準法施行規則や各自治体の条例で定められた書類を漏れなく揃える必要があります。
以下、主要な必要書類をチェックリスト形式でまとめました。
| 書類名 | 概要 | チェック |
| 完了検査申請書 | 完了検査を受けるための基本書類 建築主や施工内容、建物概要を記載 |
□ |
| 委任状 | 建築主が代理人に申請手続きを任せる場合に必要 | □ |
| 施行写真 | 構造耐力上主要な部分や工事過程を記録した写真 検査当日に確認できない箇所を補足 |
□ |
| 軽微な変更説明書 | 建築確認申請時の計画から軽微な変更があった場合、その内容と理由を説明 | □ |
| 建築設備工事監理状況報告書 | 電気・給排水設備など建築設備が設計どおり適切に施工されたことを証明する報告書 | □ |
| 省エネ基準工事監理状況報告書 | 省エネ基準に適合するよう施工されたことを証明する報告書。完了検査時に提出 | □ |
| 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 | 確認申請時に提出した省エネ計画から軽微な変更が生じた際に提出する補足書類 | □ |
| 施工結果報告書 | 施工内容の記録・結果をまとめた報告書 主に高層・大規模建築物で必要 |
□ |
| 工事監理報告書「構造関係」 | 構造部分の施工が適切に監理されていたことを証明する書類 | □ |
| 鉄骨工事報告書 | 接合部の検査記録、溶接技術者の資格証明書などを添付 | □ |
| その他必要書類 | 自治体の条例や審査基準で追加指定される場合あり | □ |
完了検査の流れと手続き
完了検査は、建築工事がすべて完了した段階で、建築主または代理人が申請を行うことから始まります。ここでは、以下に沿って完了検査の流れと手続き内容について解説します。
- 工事の完了確認:施工が設計どおり完了したか最終確認する段階
- 申請と書類提出:完了後4日以内に必要書類を揃えて申請する手続き
- 現地調査の実施:検査員が図面と施工内容を照合し適合性を確認
- 検査結果の通知:合格なら次へ、不適合は是正や再検査が必要
- 検査済証の受領:適法性を証明する書類を受け取り正式に使用可能に
工事の完了確認
建築物に関するすべての工事が終了した段階で、工事監理者や現場監督が施工内容を最終確認します。この確認は、工事が設計図書や仕様書どおりに実施され、なおかつ建築基準法など関連法規を遵守し、完了していることを確かめるためのものです。
完了検査の申請・書類提出
工事完了後は、4日以内に完了検査の申請を行う必要があります。一部の自治体(京都・大阪など)では、検査日程の事前予約が必要なため、管轄機関のルールを事前に確認しておきましょう。
なお、実際の手続きは建築主本人が行うのではなく、施工を請け負ったハウスメーカーや工務店が代理人として申請するのが一般的です。
現地調査の実施
申請が受理されると、7日以内に現地検査が実施されます。この際は工事監理者や施工者の立会いが必要で、検査員が建築確認申請の図面や仕様どおりに施工されているかを確認します。
また、検査対象は、建物本体だけでなく、寸法や材料の品質、防火・避難設備、省エネ基準の適合状況など多岐にわたります。検査は通常30分から1時間程度で行われ、目視による確認のほか、メジャーなどを使った寸法測定や各種設備の動作確認など、複数の方法でチェックします。
現地調査について詳しくは「現地調査の記事」をご覧ください。

検査結果の通知
検査で問題がなければ、検査済証(合格証)がその場、または後日交付されます。一方、図面との不整合や法令違反の疑いなど、規定への適合が確認できない場合は、検査済証を交付できない旨の通知書が発行されます。不合格となった場合、指摘事項を是正し、改めて検査を受けなければなりません。
検査済証の受領
検査に合格すると検査済証が交付されます。これによって建物の使用を正式に開始できるほか、住宅ローンの融資や不動産登記などの各種手続きも進められるようになります。
なお、検査済証が交付されるまで建築物の利用は認められません。そのため、検査済証の取得は、建物を引き渡し・使用開始するための絶対条件といえます。
完了検査でよくある指摘ポイントと注意点
完了検査では、建築物が法令を遵守し、安全に使用できる状態であること確認するため、多岐にわたる項目がチェックされます。ここでは、以下に重点を置いて、完了検査で指摘されやすいポイントや注意点をご紹介します。
完了検査でみられる代表的な箇所
完了検査の基本は、建築物が確認申請時に提出した設計図書どおりに施工されているかを確認します。検査は詳細なチェックリストにもとづいて行われ、戸建て住宅の場合はおおむね30分から1時間程度で完了します。
以下、完了検査で重視される箇所、指摘されやすい箇所を見ていきます。
図面との整合性
建築物が申請時の設計図面と一致しているかを照合します。建物の配置や各部屋の寸法、窓やドアの位置といった基本的な項目に加え、構造耐力、防火性能、避難経路などの安全性に関する規定が遵守されているかも厳格に確認されます。
内外装材
内装・外装に使われている建材が申請された仕様どおりかをチェックします。具体的には、石膏ボードや壁紙などの内装材、外壁材、防火認定を受けた仕上げ材などが設計どおりか確認します。
木造の部分
建物の安全性を担保する構造部分の適合性は、とりわけ重点的に確認されます。木造建築の場合、柱の径や筋かいの設置状況、必要な壁量、基礎の仕様などが基準どおり施工されているかを細かくチェックします。
変更を行う場合:「軽微な変更説明書」を完了検査申請前に提出
建築確認後に設計変更が発生した場合、その内容が「軽微な変更」に該当するものであれば、完了検査申請前に「軽微な変更説明書」を作成し、申請書に添付して提出する必要があります(建築基準法施行規則第4条第1項第5号)。
この説明書には、変更箇所を漏れなく記載します。確認済証の交付後に行った変更も含め、変更点をすべて明確に示さなければなりません。
なお、変更の内容が建物の構造、安全性、用途、避難経路など、建築基準法の根幹に関わる場合は「軽微な変更」とは認められません。そうした場合は、「計画変更確認申請」を提出し、新たに「計画変更確認済証」を受け取る必要があります。
軽微な変更かどうかは事前の確認が必要で、誤ると再申請や工期の遅れにつながるため注意しましょう。
是正指示が出た場合の対応と再検査の流れ
完了検査で不適合の指摘を受けた場合、指摘された箇所を設計図書どおりに修正するか、または法令に適合するよう計画変更の手続きを行います。
修正が完了したら、改めて完了検査を申請し、再検査を受けます。場合によっては、建築基準関係規定に適合していることを説明する追加書類の提出を求められるため、事前に準備しておきましょう。
これらの手続きを経て適法性が確認されれば、再検査の結果として、検査済証が交付されます。
不適合を放置したままでは、検査済証が発行されず、建物の使用や融資・登記に支障をきたすため、是正対応は迅速に行うことが大切です。
「SynQ Remote(シンクリモート)」で完了検査をもっとスムーズに!
近年、法改正の影響で完了検査に必要な手続きや審査がより厳しくなりました。工事中に設計内容を変更した際の申請や、検査で必要な写真・書類の整理、検査員からの指摘への対応など、現場管理の負担が以前よりも増しています。
これまで完了検査は、検査員と現場監督が同じ現場に立ち会い、建物が設計図面や法令どおりに施工されているかを直接確認するのが基本でした。
しかし、現場監督は複数の現場を担当することが多いため、移動や日程調整に時間がかかり、検査の遅れや確認漏れが発生するケースも少なくありませんでした。
こうした課題を解決すべく、2022年(令和4年)には国土交通省が建築基準法の運用を見直し、完了検査や中間検査における遠隔立ち会いが正式に認められる仕組みを導入しました。
タブレットやスマートフォンなどを使い、現場の映像をリアルタイムで共有できれば、現地に行かなくても検査に立ち会えるようになったのです。
このリモート検査をよりスムーズにするために役立つのが、建設現場専用のビデオ通話ツール「SynQ Remote(シンクリモート)」です。本ツールは映像共有に最適化されているだけでなく、写真やメモを一元管理できる記録システムも搭載しており、日々の施工記録の整理や新人監督への引継ぎ、検査準備を効率化できます。
完了検査をより確実かつ、効率的に進めたい方は、ぜひ「SynQ Remote」のサービスページをご覧ください。現場管理の新しいスタンダードを、一度体感してみませんか。