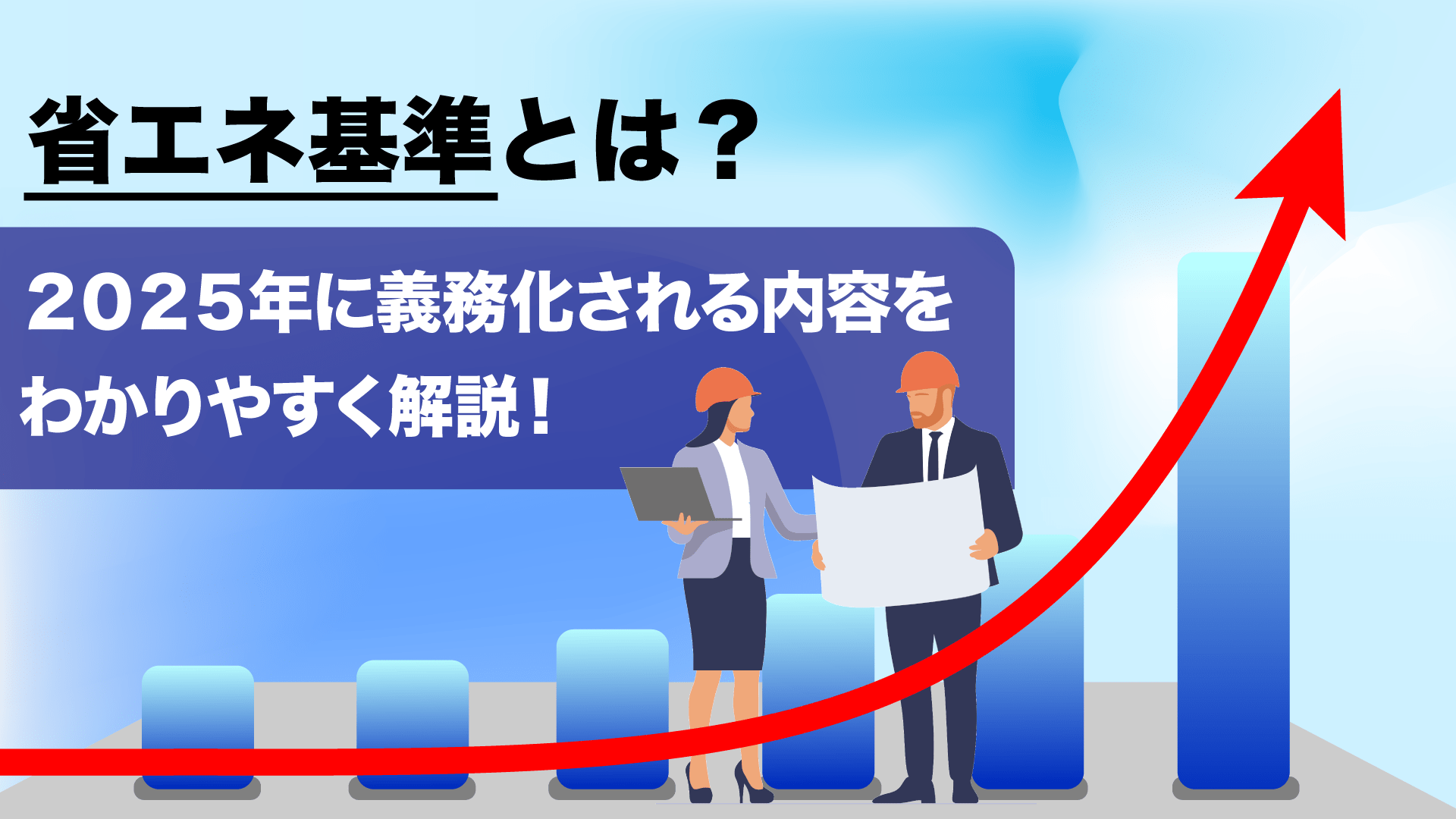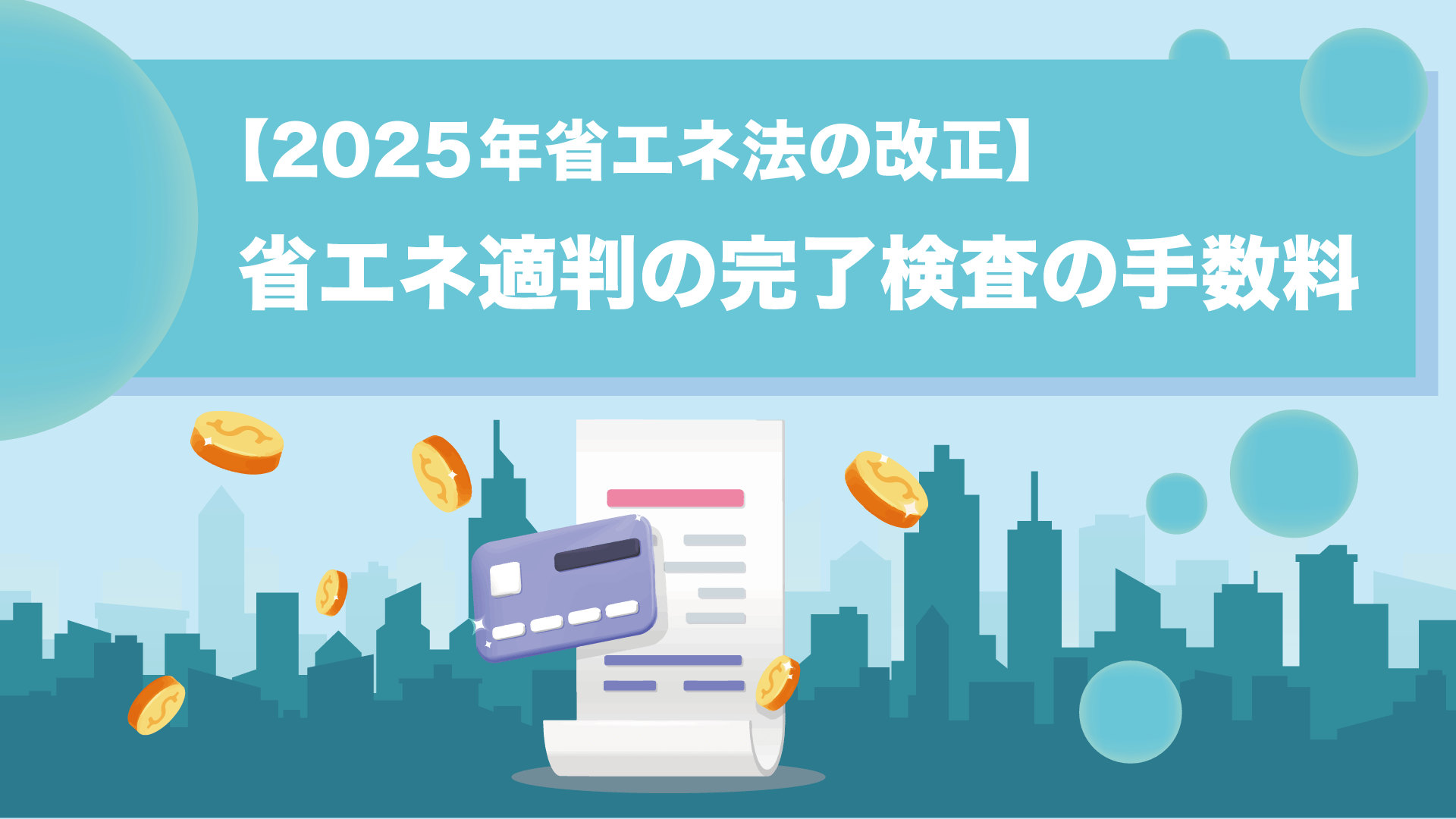省エネ適判完了検査とは?必要事項や手続きの流れをわかりやすく解説!
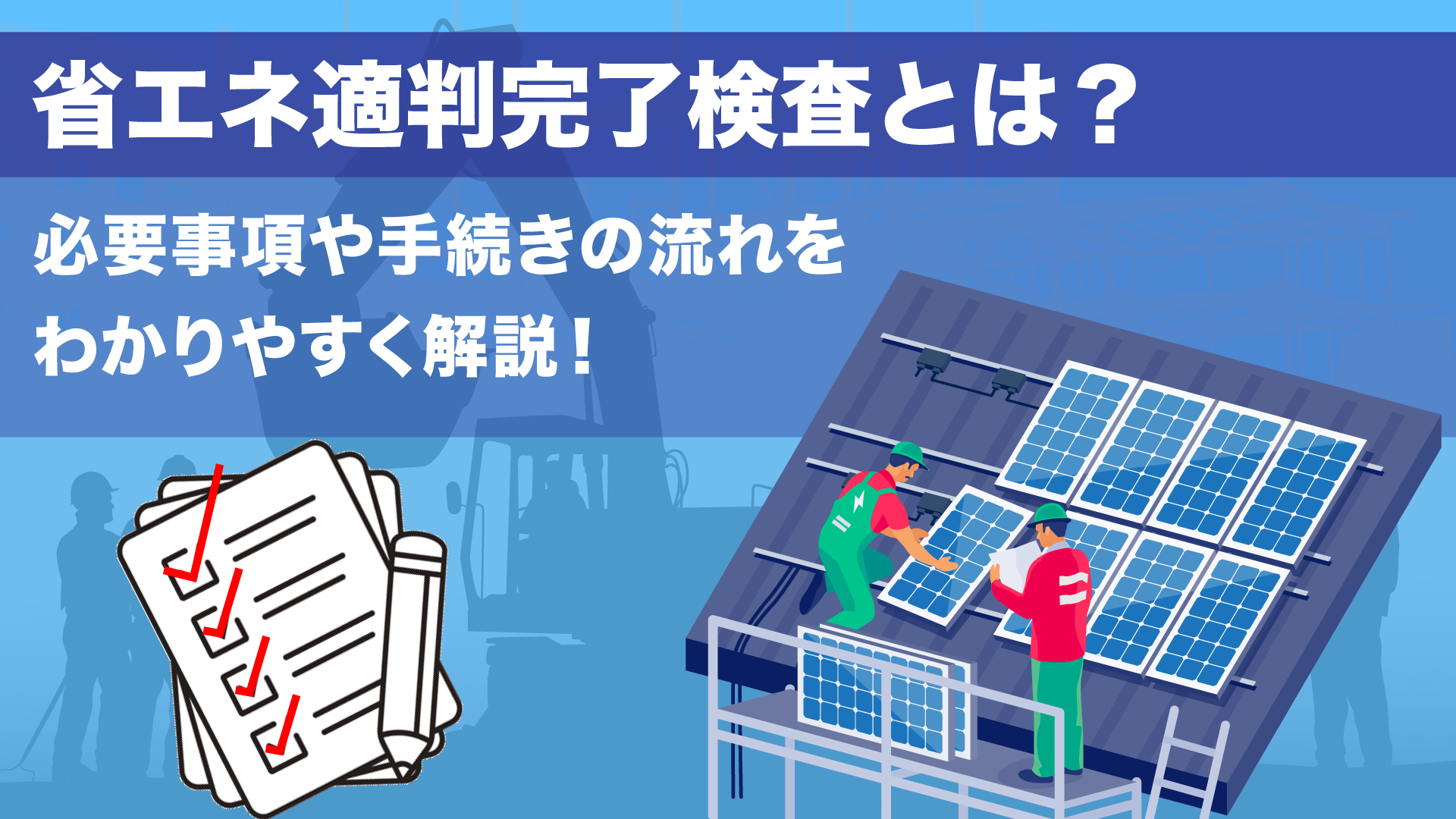
2025年4月から、省エネ基準への適合がすべての新築建築物で義務化され、「完了検査も必須になる」と聞いて戸惑っている方も多いのではないでしょうか。これまで説明義務や届出義務にとどまっていた小規模建築物や住宅も、今後は法的に省エネ基準への適合が求められるようになります。
今回は、省エネ適判完了検査の概要から、手続きの流れ、必要書類、現場での確認ポイント、よくある不適合例、そして効率的に進めるための準備・体制まで、実務に直結する視点で解説します。
制度変更に備えて、実務対応の見直しや情報整理を進めている設計・施工担当者の方は、ぜひご一読ください。
省エネ適判完了検査とは?建築物の省エネ基準適合を確認する手続き
省エネ適判完了検査とは、建築物省エネ法にもとづく「適合性判定」を受けた建築物について、実際の施工段階で省エネ基準に適合しているかを確認する検査です。
この制度は、建築分野における温室効果ガスの排出削減を促進し、国が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現を目指して導入されました。
検査で基準に適合していない点が確認された場合、その建築物には使用認可が下りない仕組みとなっており、厳格な制度運用が行われています。
今一度、省エネ適判完了検査の基礎知識をおさらいしていきます。

建築物省エネ法の改正によって2025年4月から義務化
建築物省エネ法の大幅な改正により、2025年4月1日以降に着工するすべての新築建築物に、省エネ基準への適合が義務づけられます。
非住宅建築物については、2017年の建築物省エネ法施行時に「延べ床面積2,000平方メートル以上の建物」が適合義務の対象とされていましたが、2021年4月の改正により「延べ床面積300平方メートル以上の建物」に対象範囲が拡大されました。そして今回、2025年4月の改正で「300平方メートル以下の小規模物件」も加わり、完全義務化となります。
また、住宅に関しても大きく見直されました。従来は、「300平方メートル以上の住宅」に届出義務があり、それ未満の住宅は説明義務の対象とされていました。しかし、今回の改正で建物の規模にかかわらず、「すべての住宅において省エネ基準の適合」が求められるようになります。
2025年4月1日から、届出制度や説明制度は廃止され、省エネ基準への適合義務制度に統一されます。建築確認の段階から完了検査にいたるまで、省エネ性能の確認が一貫して求められ、基準を満たさない建物には確認済証が交付されなくなります。
2025年の建築基準法改正では、省エネ基準適合義務化を含む重要な変更点が多数あります。詳しくは「【2025年建築基準法改正】変更ポイント・対策をわかりやすく解説」をご覧ください。
検査方法は書類検査と現場検査の2種類ある
省エネ適判完了検査には、「書類検査」と「現場検査」といった2種類の検査方法を採用しています。
書類検査ではまず、検査実施機関へ完了検査申請書、省エネ適判に用いた図書、軽微変更説明書等の必要書類・資料を提出します。検査機関で提出書類の妥当性や内容統一性が審査され、記載ミスや不足があれば再提出を求めます。
そして現場検査は、書類検査等の結果に応じて行うものです。設備機器の設置状態や型番確認を目視で行うほか、提出書類と実際の施工状況が一致するか確認します。この検査において、計画段階で想定していた設備の未設置、想定外設備の存在、機器仕様や消費電力の相違などがあれば変更手続きが必要となります。

省エネ適判完了検査の手続きの流れ
省エネ適判完了検査では、書類審査と現場検査を通じて、省エネ性能が設計通りに確保されているかを総合的に評価します。ここでは、省エネ適判完了検査の一般的な流れをご紹介します。
| ステップ | 段階の名称 | 主な内容・アクション | 主要提出書類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 設計段階での適合判定(適判) | 省エネ性能確保計画の策定・提出、適合判定の取得 | ・適合性判定申請書 ・エネルギー消費性能計算書 ・設計図書一式など |
| 2 | 施工段階での確認 | 設計内容に基づいた工事実施、計画通りの設備設置、写真記録 | ・工程写真 ・軽微変更届(該当時) |
| 3 | 完了検査の申請 | 工事完成後、適合判定機関等へ完了検査を申請 | ・判定結果通知書 ・完了図(竣工図) ・設備仕様書など |
| 4 | 検査の実施 | 検査員による現場確認(外皮性能、設備性能、設計整合性) | なし(主に現地確認) |
| 5 | 検査結果の通知 | 検査結果の通知、合格で検査済証交付、不合格で是正措置 | なし(結果通知) |
設計段階での適合判定(適判)
工事開始前の必須手続きとなるのが、建築物の省エネ適合性判定(適判)です。建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画を策定し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ提出して適合性判定を受けます。この時点で省エネ基準への適合が確認されなければ、建築確認の確認済証が発行されず、工事を開始することはできません。
申請時には多くの書類が求められます。以下が主な提出書類です。
- 省エネ適合性判定申請書
- エネルギー消費性能計算書
- 設計内容説明書(設計概要書)
- 設計図書一式(図面)
- 仕様書・仕上書
- 一時エネルギー消費量算定プログラムによる入力結果・出力帳票
- 設計者の資格署名書(写し)
- 委任状(任意)
施工段階での確認
施工段階では、適合判定で認められた設計内容に基づいて工事を進めます。断熱材や空調設備、照明設備など、設計図書に記載された内容が計画通りに設置されているかを各工程で確認することが重要です。
特に重要なのが、各工程における写真記録の保存です。断熱材の施工状況や設備機器の設置状況は、完成後には目視で確認することが難しいため、詳細な記録を残すことが求められます。
工事監理者は、省エネ基準に関わる項目について、常に設計図書との整合性を確認しながら工事を監理します。変更が生じた場合、その内容に応じて速やかに手続きをしなければなりません。
また、施工中に計画変更が発生した際には、それが軽微変更に該当するかを判断し、必要であれば軽微変更届などの手続きを行います。
完了検査の申請
建築工事の完成後には、適合判定機関または所管行政機関に対して完了検査を申請します。この検査では、設計段階で認可された省エネ基準に対して、実際の施工が適合しているかを確認するための書類を提出します。
完了検査申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
- 省エネ適判の判定結果通知書
- 完了図(竣工図)
- 設備機器の仕様書
- 工程写真(断熱材・設備等)
- 軽微変更届(該当する場合)
施工中に、設計内容に変更があった場合、軽微変更に該当する内容についてはその届出書を提出しましょう。
検査の実施
完了検査では、検査員が建築現場を実際に訪問し、外皮性能や設備の省エネ性能について現地で確認します。検査の中心は目視による確認ですが、断熱材の厚み測定や設備性能の数値確認など、必要に応じて計測も行われます。
具体的な検査内容としては、断熱材の材質や厚みが設計図書と一致しているかどうか、空調や照明などの設備機器の性能が計画通りであるか、そして設計図と実際の施工状況との整合性に問題がないかどうかを確認します。
検査結果の通知
完了検査が適正に終了すると、その結果が正式に通知されます。合格の場合、建築物は省エネ基準を満たしていることが公式に認定され、検査済証が交付されます。
一方、不合格となった場合は、速やかに是正措置をおこなう必要があります。主な不合格の要因にはいくつかのパターンがあります。
主な不合格要因としては以下が挙げられます。
- 設計計算の誤りによる計算上の不適合(計算過程での入力ミスや計算ミス)
- 設計図面と施工内容の不一致(断熱材の種類や厚みが異なるなど)
- 提出書類の不備(書類不足や記載内容の誤り)
不合格となった場合には、原因に応じて設計の修正や再申請が必要です。軽微変更が必要な場合は、その手続きを経た後に再検査を受ける必要があります。こうした対応には追加の時間と費用が発生するため、あらかじめ十分な準備・確認を行っておきましょう。

省エネ適判を受けてから、完了検査までに変更点があった場合
省エネ適判の認可を受けた後、実際の施工段階に入ってから計画内容に変更が生じるのは、現場ではよくあるケースです。こうした変更が発生した場合、その内容や規模に応じた適切な手続きを行います。具体的に見ていきましょう。
変更内容によって対応が3つに分けられる
省エネ適判の認可を受けた後、計画に変更が生じた際は、その変更内容に応じて以下の3つのルートに分類されます。
| 分類 | 変更内容 | 提出書類 |
|---|---|---|
| ルートA | 省エネ性能が向上する変更 | 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書、添付図書 |
| ルートB | 一定範囲の省エネ性能が低下する変更 | 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書、添付図書 |
| ルートC | 再計算によって基準適合が明らかな変更 | 上記2つに加えて、軽微変更該当証明書(登録省エネ判定機関(ERI)より交付を受ける) |
この分類制度は、計画変更による省エネ性能への影響を適切に評価し、必要最小限の手続きで完了検査を進められるように設計されたものです。それぞれのルートごとに、提出書類や申請手続きが異なるため、変更内容を正しく判断しましょう。
ルートAは、省エネ性能が向上する変更が対象です。具体的には、建築物の高さや外周長の減少、外皮性能の向上、設備機器の効率改善などが該当します。この場合は再計算が不要で、「軽微な変更説明書」と関連図書を提出すれば、完了検査を受けられます。
ルートBは、省エネ性能が一定の範囲内で低下する変更が対象です。変更前の計画で省エネ性能が基準値を10%以上上回っており、変更後の性能がその範囲内(10%以内)に収まる場合に適用されます。たとえば、空調設備においては、外壁かつ窓の平均熱貫流率の増加が5%以内、かつ熱源機器の平均効率の低下が10%以内の両方の条件を満たす場合に、このルートで対応します。
ルートCは、ルートA・Bの条件に当てはまらない変更であっても、再計算によって基準適合が確認された場合に適用されます。この場合、「軽微変更該当証明書」の取得が必要となり、登録省エネ判定機関(たとえばERI)から証明書の交付を受ける必要があります。あわせて、省エネ適判機関や所管行政庁への申請と、所定の手数料の支払いも必要です。
各ルートで必要となる提出書類や手続きが異なるため、変更内容を正確に判断し、適切な対応を取りましょう。誤った分類や手続き漏れがあると、完了検査時の遅延や再手続きにつながるおそれがあります。
変更後に完了検査が通らない場合に考えられる原因
近年は完了検査における不適合事例が増加傾向にあります。なかでも多く見られるのが、「施工者・設計者の情報共有不足」です。
施工現場では、さまざまな理由から計画変更が必要になることがありますが、その変更内容が設計者に正確に伝達されていないケースが少なくありません。
たとえば、施工者の判断で内容を変更したものの、設計者側がその事実を把握しておらず、完了検査時に整合性が取れないトラブルが発生しています。このような問題を防ぐには、定期的な打合せの実施と、変更内容の文書化による情報共有体制の確立が不可欠です。
また、完了検査時点で最終図面が未完成のときも、注意が必要です。施工中に設備や仕様に変更があった場合、図面に反映されていなければ、省エネ計算と実施工に齟齬が生じます。この問題を防ぐには、施工の進捗に応じて図面を段階的に更新し、完了検査申請前に必ず図面の最終確認を行いましょう。
さらに再計算に使用した図面と、実際の現場の状態に差異がある際、完了検査が通らないことがあります。ブラインドを設置する計画だったのに未設置であったり、計算書に記載された制御システムが実際には導入されていなかったりすると、完了検査に通りません。
これらの問題を防止するためには、省エネ計算書と現場の設備仕様を照合するチェックリストを作成し、完了検査前に現地確認を徹底することが大切です。

省エネ適判完了検査の効率的な進め方
省エネ適判完了検査を効率よく進めるためには、事前準備の徹底、デジタルツールの活用、そして遠隔臨場(リモート立会検査)の導入が効果的です。これらを組み合わせることで、検査にかかる期間の短縮と、検査品質向上を同時に実現できます。
- 検査項目を明確化し事前準備を徹底する
書類整理や関係者共有で検査準備を万全に整える - デジタルツールを活用し認識のズレや手間を減らす
デジタルツールで情報共有を効率化し、ミスを防止 - 遠隔臨場を導入して手間やコストを減らす
遠隔臨場で移動コストを削減し、検査を迅速化
検査項目を明確化し事前準備を徹底する
省エネ適判完了検査を円滑に進めるためには、検査実施前の準備作業が欠かせません。以下の4つの準備を徹底することで、検査を円滑に進めることができます。
書類の整理
第一に重要なのが、必要書類の整理と保管体制の構築です。適判申請時に提出した計画書類や設計図書、設備仕様書などは、完了検査時の照合作業において中核的な役割を果たします。これらの書類を体系的に整理・保管しておきましょう。
関係者への共有
設計担当者や施工管理者、検査実施者など、プロジェクトの関係者に対し、検査の目的や実施内容を事前に共有しておくことで、当日の検査をスムーズに進められます。
チェックリストの作成
検査項目の一覧化とチェックリストの作成も効果的です。省エネ計算に計上された設備や、計上すべき設備が現場で正しく設置されているかを確認するために、目視・計測・書類といった確認手法ごとのチェックリストを作成すると、検査の網羅性が確保され、確認漏れを防ぎやすくなります。
法的要件の確認
建築物省エネ法や関連する技術基準の最新動向を把握し、計画段階から施工完了までに発生した変更点について、必要な手続きが完了しているかを確認しておきます。軽微変更があった場合は、ルートA・B・Cいずれに該当するかを正確に判断し、それに応じた適正な手続きが完了しているかチェックしてください。
これらの事前準備を徹底することで、検査にかかる時間(リードタイム)の短縮が期待できるでしょう。書類不備による再提出のリスクを大幅に減らすとともに、検査当日の作業効率も向上しやすくなります。
デジタルツールを活用し認識のズレや手間を減らす
省エネ適判完了検査では、指示内容が現場に、正確に伝わらないトラブルがたびたび発生します。特に、経験の浅い現場担当者やクライアントとのやり取りでは、電話や口頭での説明だけでは理解に差が出やすく、作業効率の低下や認識の齟齬によるミスにつながるリスクが高まります。
これらの課題を解決するためには、デジタルツールの活用が有効です。チャットツールやタスク管理システムを導入すれば、すべての連絡事項がテキストとして記録・保存され、あとから何度でも確認できる履歴として残ります。これにより、記憶違いや伝達ミスを防止し、関係者間の認識のズレを大幅に軽減できます。
加えて、ビジネスデジタルツールはリアルタイムの情報共有にも対応しています。たとえば、検査中に不具合や設計との不一致が発覚した場合でも、現場から即座に状況を関係者へ共有でき、迅速な対応方針の決定・実行が可能です。
ビジネスチャットツールについて詳しくは「ビジネスチャットツールとは?導入するメリットやツールを解説」をご覧ください。
遠隔臨場を導入して手間やコストを減らす
遠隔臨場技術を導入することで、検査員がオフィスや遠隔地から複数の現場をリモートで確認できるようになり、1日あたりの検査対応件数が増加します。その結果、プロジェクト全体のスケジュール管理が効率化され、検査を迅速に行えるようになります。
現場作業員の待機時間を大幅に短縮できるのもポイントです。従来は検査員の到着を待って作業が中断される場面もありましたが、事前調整にもとづいて検査が実施されるため、現場の作業継続性が保たれます。
また、映像技術とクラウドシステムの連携により、検査中に取得した映像・計測データをリアルタイムで共有・保存できます。記録作成や報告書作成の時間を大幅に短縮し、検査完了から報告提出までのリードタイムを短縮できるでしょう。
さらに現地担当者と遠隔地の専門家が容易に連携できるため、スケジュール調整の柔軟性が向上します。地理的制約を解消することで、専門知識を持つ技術者が必要なタイミングで検査に参加できるほか、複数の専門家が同時に確認を行うことも可能になります。
遠隔臨場は、検査の在り方を大きく変える有効な手段として、今後の建設業における標準的な運用手法となりつつあります。詳しくは、「遠隔臨場とは?注目されている背景や導入メリット、注意点を紹介」をご覧ください。

省エネ適判完了検査の効率化には「SynQ Remote」がおすすめ
本記事で紹介したように、適正な手続きと事前準備を進めることが、省エネ適判完了検査をスムーズに通過するためのポイントとなります。検査書類の整理や関係者間の情報共有、変更管理、そして現場との整合性確認など、検査にかかる実務負担は決して小さくありません。
こうした現場の課題を解決するツールとしておすすめなのが、遠隔サポートツール「SynQ Remote(シンクリモート)」です。
「SynQ Remote」は、クラウドと映像技術を活用したコミュニケーションツールで、検査担当者が現場に足を運ぶことなく、遠隔で検査立会いや現場確認を行うことが可能です。リアルタイムでの情報共有により作業効率が大幅に向上し、検査の記録や報告書作成などをツール上で完結させられます。
移動コストや調整負担を抑えながら、検査の品質とスピードを両立できる本ツールは、検査業務の省力化だけでなく、働き方改革の実現にも貢献します。これからの検査対応に、ぜひ「SynQ Remote」の導入をご検討ください。