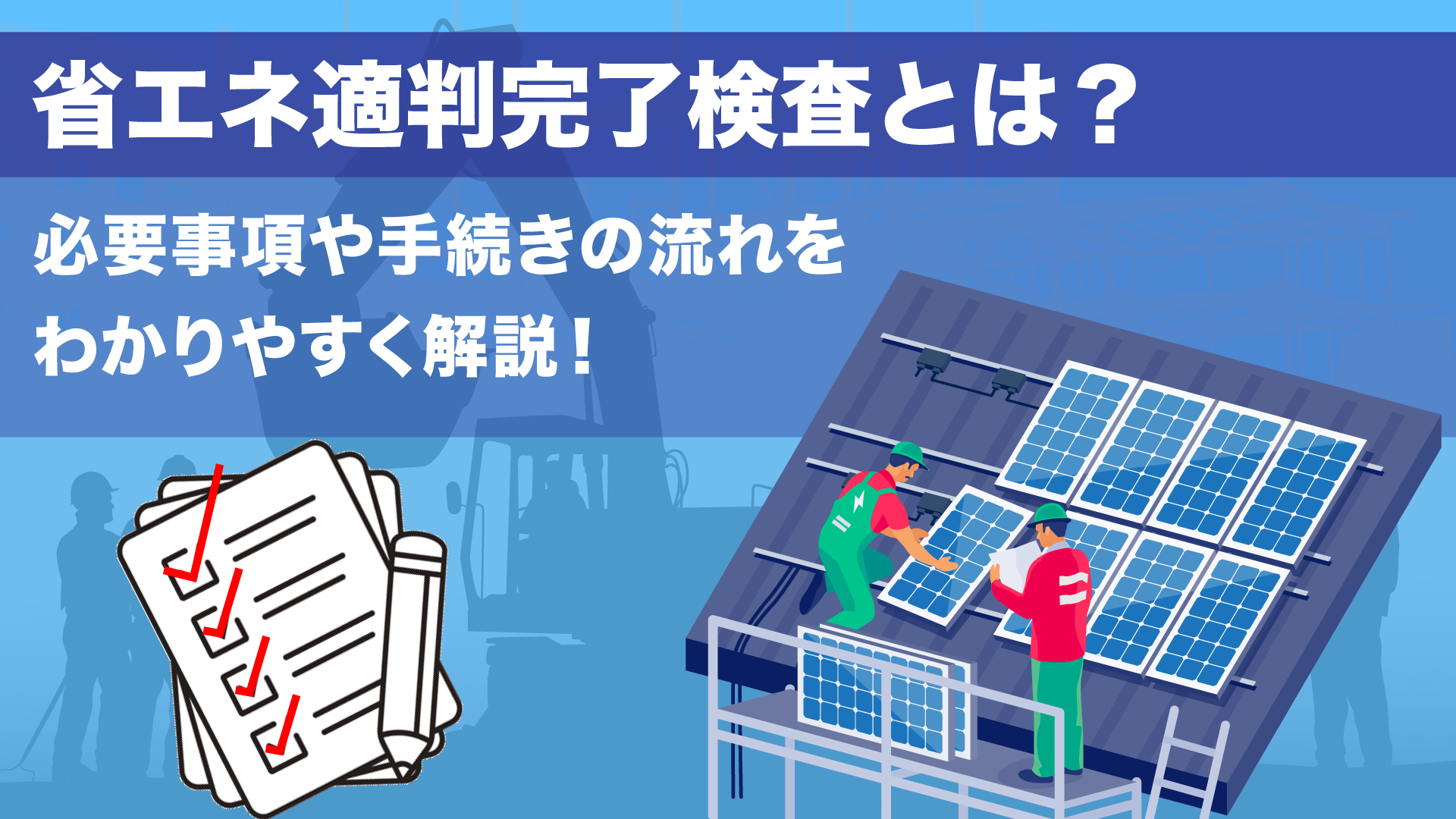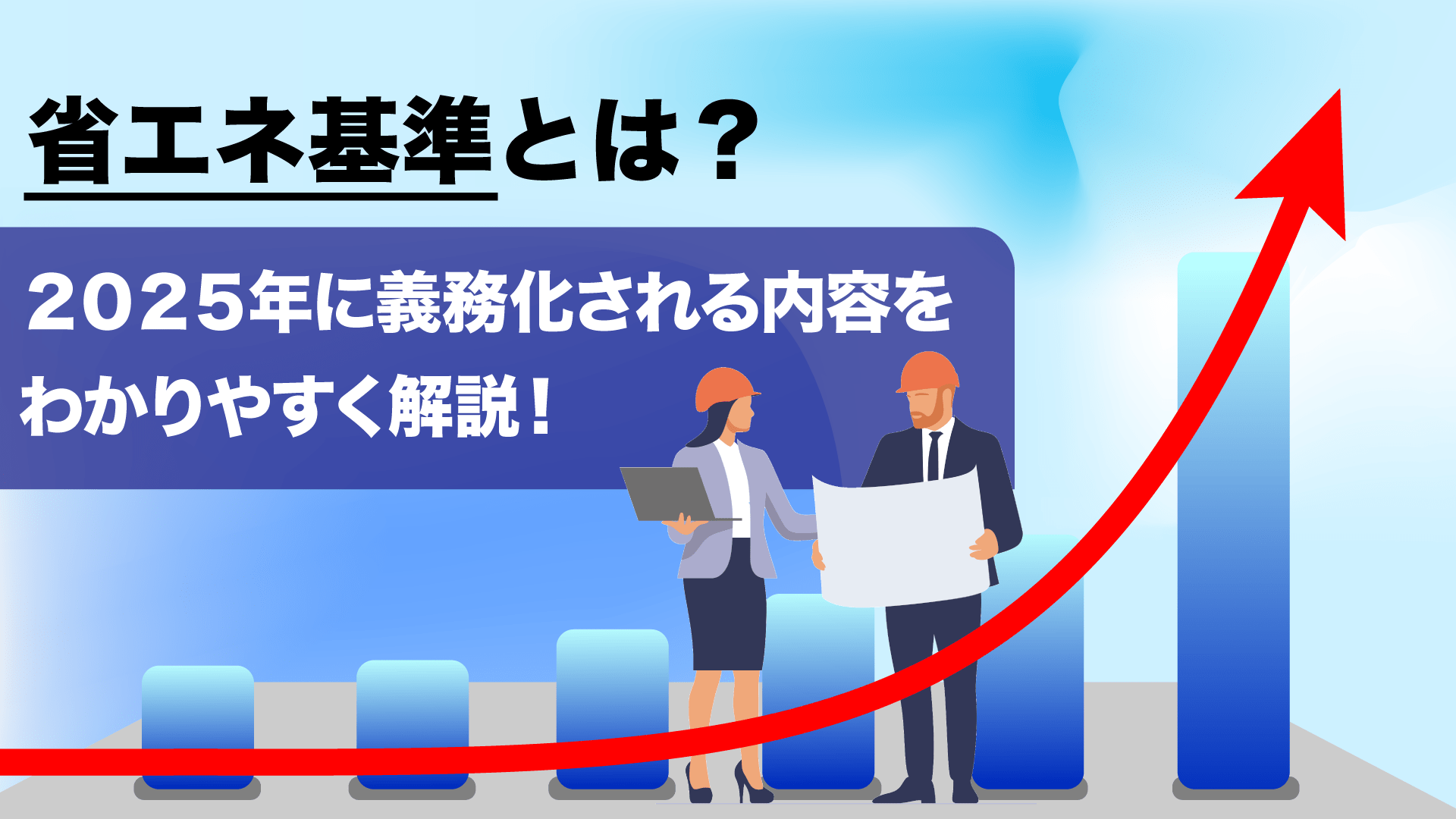【2025年省エネ法の改正】省エネ適判の完了検査の手数料
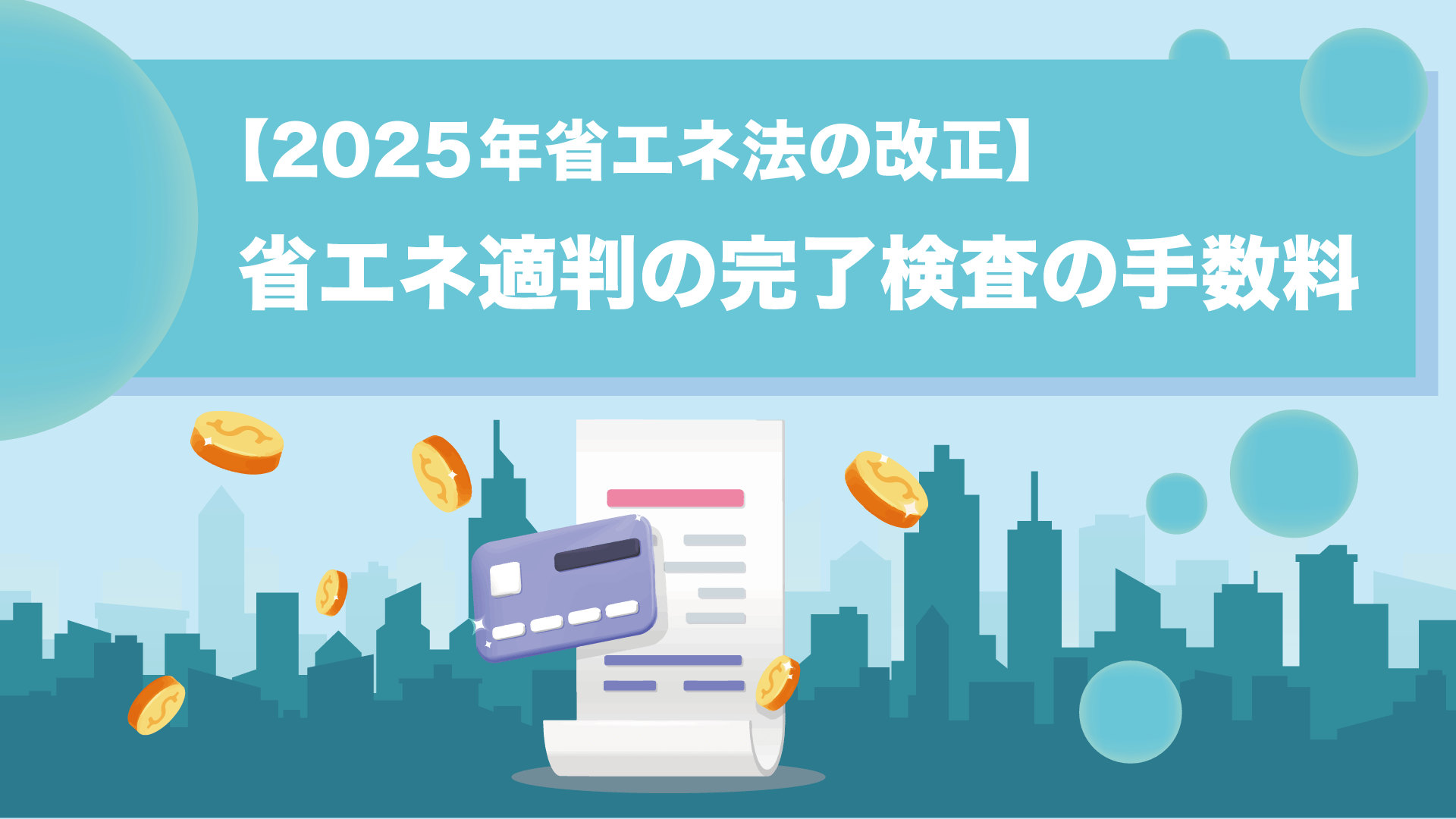
令和7年4月の建築物省エネ法改正により、「省エネ適判(省エネ適合性判定)」がすべての新築建築物で義務化されました。なお、同時期に建築基準法も改正され、建築確認手続きの対象範囲が拡大されています。これにより、完了検査にかかる手数料にも変化が生じています。
しかし、「実際にどれくらいの費用が発生するのか把握できず、予算を立てにくい」と感じている建築士や設計担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、省エネ適判の概要から完了検査の流れ、2025年改正による手数料の変更点や建築プロジェクトへの影響、さらに具体的な対応方法を解説します。
省エネ適判(省エネ適合性判定)とは?
省エネ適判とは、建築物のエネルギー消費性能が法定の省エネルギー基準に適合しているかどうかを確認する制度です。断熱性能や空調・給湯などの設備機器のエネルギー効率といった設計内容をもとに、工事着工前にその計画が基準に適合しているかどうかを審査します。
2025年4月の法改正により、この制度の適用対象は大きく拡大されました。新築だけでなく、増改築をともなうすべての建築物に対しても義務化され、建築業界全体で省エネ性能の確保と環境配慮が一層求められるようになっています。
建築主は、工事に着手する前に「建築物エネルギー消費性能確保計画書」を作成し、所管行政庁または登録判定機関に提出する必要があります。そのうえで、当該計画が省エネ基準に適合しているかどうかの判定を受け、適合と認められる必要があります。

出典:今後の住宅・建築物における省エネ対策のあり方(第三次答申)、建築基準制度のあり方(第四次答申)に向けた主な審議事項と議論の方向性
近年では、省エネ適判の制度浸透にともない、基準に適合する建築物の割合は着実に増加しています。省エネ基準適合率は年々向上しており、国土交通省の調査によると、住宅における省エネ基準適合率は2015年度の36%から2023年度には89.9%まで上昇し、非住宅では同期間に71%から99.6%まで達しています。
なお、以下の建築物は省エネ基準適合義務の対象外です
・延床面積10㎡以下の建築物
・居室を有しない建築物や高い開放性を有する建築物(車庫、倉庫など)
・文化財等の歴史的建造物
・仮設建築物
完了検査とは?
完了検査は、建築基準法に基づく完了検査の中で省エネ基準への適合確認も行われます。省エネ適合性判定で提出された計画書をもとに、実際の建築物が省エネ基準を満たしているかを確認します。
現地での確認においては、断熱材の厚さや設備機器の仕様などが、事前の計画と一致しているかどうかをチェックします。万が一、計画と異なる内容に変更されている場合には、完了検査を受ける前に、軽微変更届や計画変更申請を適切に提出しておく必要があります。
完了検査の具体的な手続きには、申請方法の確認、必要書類の準備、検査日程の調整などが含まれます。これらの準備を事前に整え、検査機関との円滑な連携を図ることが重要です。
なお、検査の結果、省エネ基準に適合していない点が確認された場合には、是正措置を講じたうえで再検査を受ける必要があります。
省エネ適合判定の完了検査について詳しくは「省エネ適判完了検査とは?必要事項や手続きの流れをわかりやすく解説!」をご覧ください。

「2025年改正後」省エネ適合判定の完了検査時の手数料
2025年4月の建築基準法改正および建築物省エネ法改正により、建築確認申請や省エネ適合性判定に関する手数料体系が多くの自治体で改定されました。
従来は一律の料金設定だった自治体でも、建築物の用途や規模、省エネ審査の有無に応じた細分化が進んでおり、審査・検査にかかる費用負担が増加するケースがあります。
手数料の主な構成
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 建築確認申請手数料 | 建築確認申請・計画通知にかかる基本手数料(建築物の用途・構造・規模によって異なる) |
| 省エネ審査手数料 | 省エネ適合性判定または仕様基準審査にかかる加算手数料(2025年改正で新設・拡大) |
| 完了検査手数料 | 工事完了後の検査費用(省エネ基準適合確認を含む) |
完了検査時にかかる手数料は、それぞれ個別に発生する仕組みとなっているため、制度改正後は全体としての費用は増加傾向にあります。非住宅に比べて手数料負担が少ないとされる住宅であっても、その費用負担は無視できません。
具体的な金額
以下は、代表的な自治体における省エネ適合性判定に関連する手数料の改正内容と、参考となる金額の目安です。
| 自治体 | 手数料 (改正前) |
手数料 (改正後) |
手数料体系 | 主な変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (板橋区) |
約19,000円 | 約28,000円 | 基本料金+省エネ評価加算 | 省エネ適判対応により追加手数料が発生 |
| 宮城県 | 約21,000円 | 約30,000円 | 住宅・非住宅別料金体系 | 床面積300㎡超〜500㎡未満区分を新設 |
| 福岡県 | 約18,500円 | 約29,000円 | 複合建築物対応料金 | 住宅・非住宅部分を合算して算出 |
※金額は、木造2階建て・延床面積150㎡程度の住宅における概算例
改正後の手数料については、いくつかの点に注意が必要です。まず、手数料の計算方式や金額は自治体によって異なるため、建築を予定している地域の所管行政庁に事前に確認してください。
また、従来の確認申請手数料に加えて、省エネ基準に関する審査や完了検査に対する追加手数料が新たに発生する点に留意しましょう。建物の用途(住宅・非住宅)や規模によって適用される手数料体系が異なる場合があるため、設計・申請の初期段階から制度内容を十分に確認し、計画に反映することが重要です。

改正が与える影響
本改正により、中小規模の建築プロジェクトでは予算計画やスケジュールに大きな影響が出る可能性があります。
まず、手数料の増加は予算に直接影響します。たとえば木造2階建て住宅の場合、従来より1万円以上高くなるケースも見られ、初期計画段階でのコスト調整が必要でしょう。
設計・施工のスケジュールにも変化が生じます。新2号建築物(主に木造2階建て住宅や延床面積200㎡超の平屋住宅など)の建築確認審査期間は、これまでの「7日以内」から「35日以内」へと延長されるため、従来の省エネ届出制度と比較して該当する建築物では工程が長引く可能性があります。
※新2号建築物とは、建築基準法改正により、従来の4号建築物(4号特例対象)から新2号建築物へと区分が変更された建築物のことです。従来簡略化されていた構造審査なども含めて本格的な審査が必要となります。
また、新制度では工事着手の21日前までに事前通知が義務化されており、この手続きが遅れると予定通りの着工が困難になるでしょう。そのため、改正後の制度に即した、計画的なプロジェクト管理がいっそう重要となります。
省エネ適合判定の手数料変更への対応方法
本改正にともない、建築主は新たな手数料体系への対応が求められています。特に中小規模の建築物では、設計・申請プロセス全体に与える影響が大きいため、計画段階から注意が必要です。
以下、建築主が押さえておくべき、手数料変更への対応方法をご紹介します。
情報収集を早めに行う
改正内容と手数料の変更点を正確に把握するため、「国土交通省」の公式リーフレットや制度解説ページを確認しておきましょう。これには制度の概要や手数料体系の変更点が明記されています。
また、建設予定地の所管行政庁が公開している「省エネ適合判定に関する手続き情報」も確認しておくと安心です。各自治体の公式サイトでは、登録省エネ判定機関の一覧や申請先に関する案内が掲載されていることが多いため、早期に調査を済ませておきましょう。

予算計画を修正する
省エネ基準への適合が義務化されたことにより、建築プロジェクトでは新たな手数料への対応が必要です。特に、「書類作成の代行手数料」と「適合性判定審査手数料」という二つの費用が新たに発生します。
省エネ計算や申請書類の作成には専門的な知識が求められるため、外部の代行業者に委託するのが一般的です。そのため、設計や申請の初期段階から、外注コストを含めた予算計画を立てましょう。
加えて、新制度では従来不要だった審査手数料や検査費用も発生します。これらの金額は建物の規模・用途によって大きく異なるため、建築予定地を所管する行政庁や登録省エネ判定機関に早めに確認し、過不足のない予算を確保しましょう。
必要書類や手続きの流れを確認
提出書類は、省エネ計算書をはじめ、建築設備に関する詳細な図面や仕様書など多岐にわたります。これらは設計の初期段階から計画的に準備する必要があり、早期の情報整理と作業分担が不可欠です。
また、新制度では、建築確認審査の期間が最大35日程度に延長されるほか、工事着手の21日前までに事前通知を行う必要があります。従来に比べて大幅なスケジュール変更となるため、余裕のある工程管理を心がけてください。
「SynQ Remote(シンクリモート)」導入で施工管理の安全管理を円滑に!
建築基準法の改正により、省エネ適判や完了検査にかかる手数料が見直されました。それにともない、検査時の現場対応や立ち合い確認の回数が増え、建築主・設計者・施工者にとっては対応コストの増加が懸念されます。
こうした課題に対して注目されているのが、現場特化型ビデオ通話ツール「SynQ Remote(シンクリモート)」です。
「SynQ Remote」を活用すれば、現場に直接赴くことなく遠隔で臨場し、検査や手続きの進捗をリアルタイムで確認できます。これにより、限られた人員でも複数現場を同時に管理でき、移動コストやスケジュール調整の負担を軽減可能です。
検査の効率化、手数料変更への対応を検討されている方は、ぜひ一度「SynQ Remote」の詳細をご覧ください。