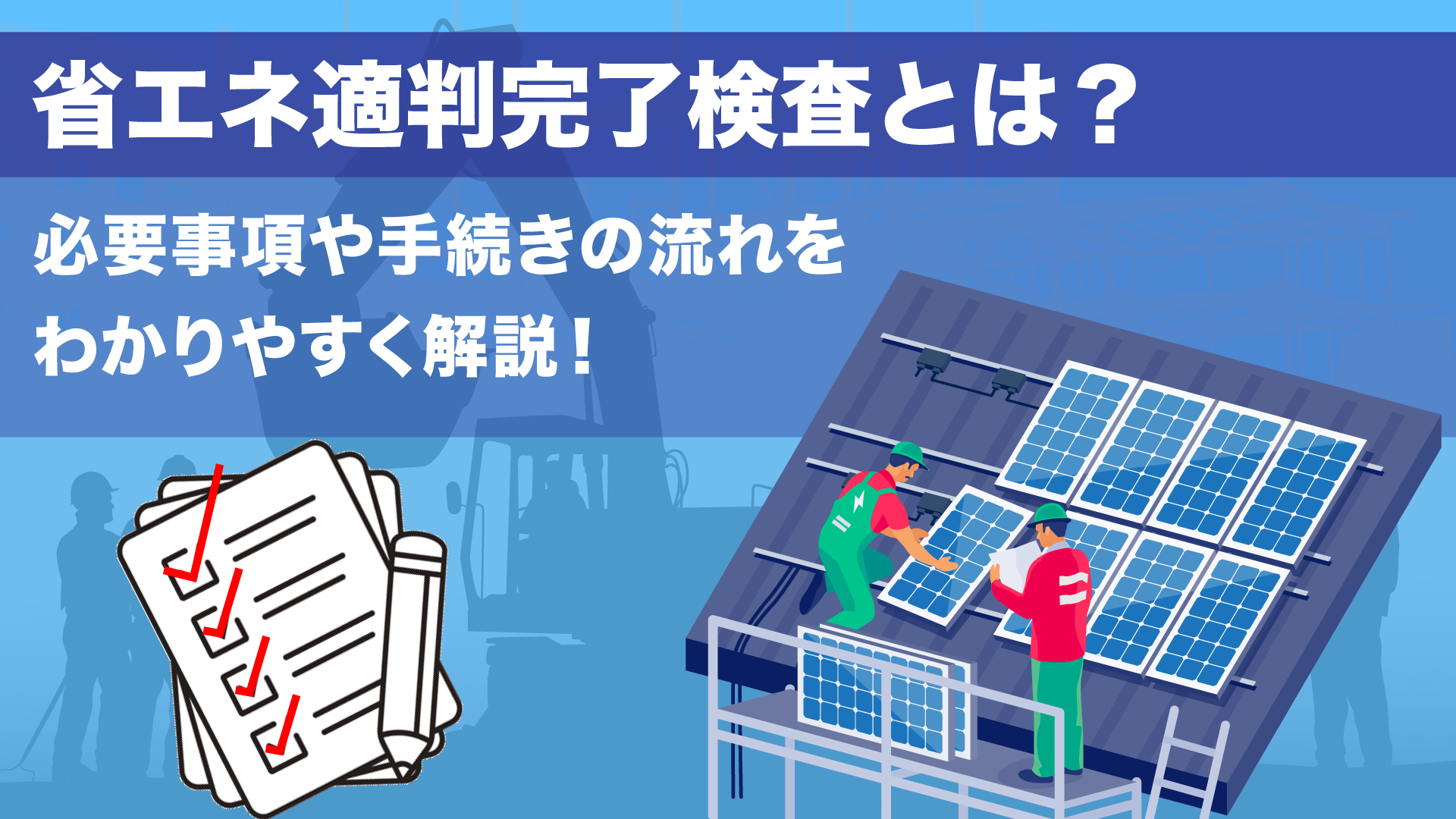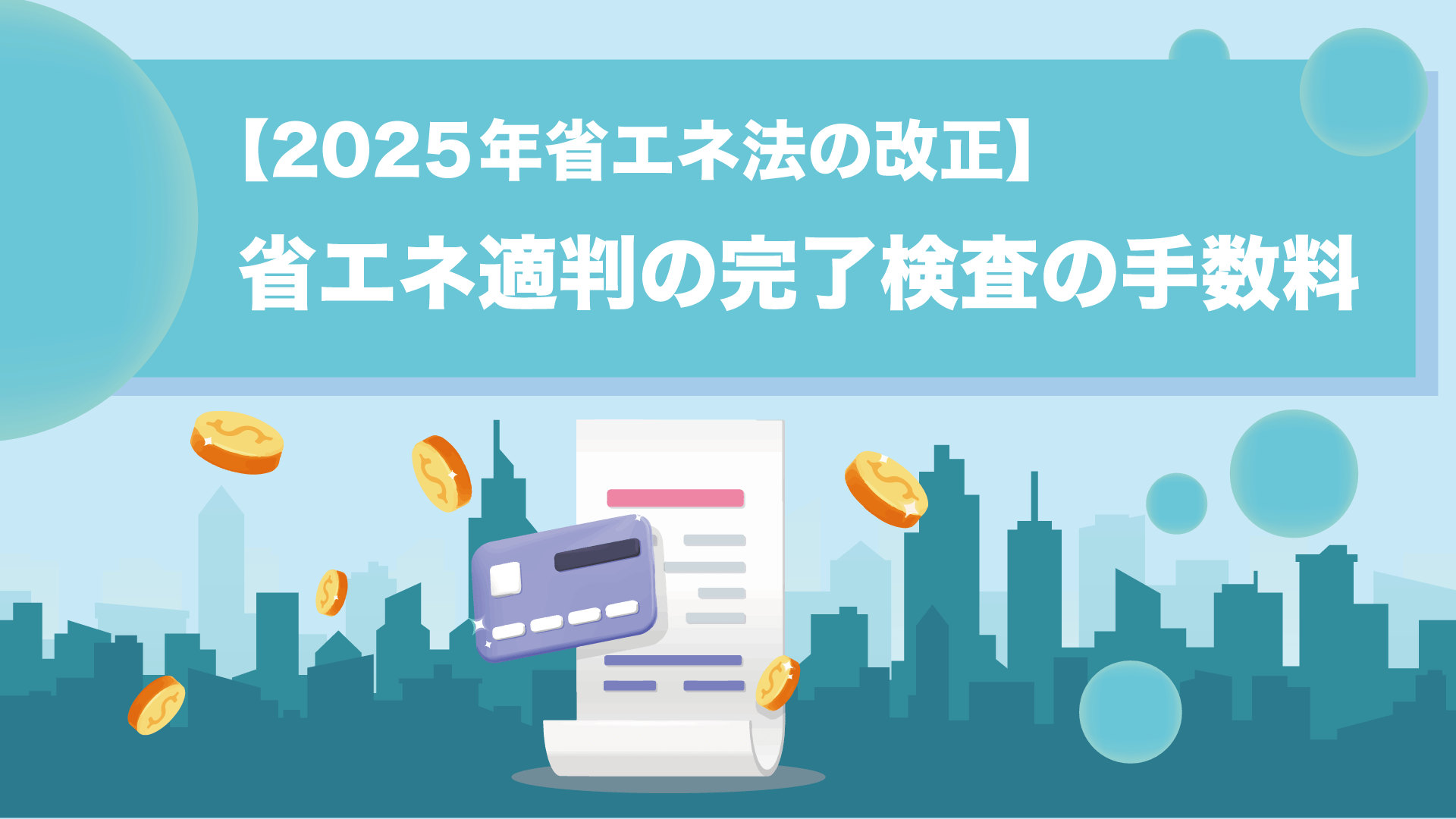省エネ基準とは?2025年に義務化される内容をわかりやすく解説!
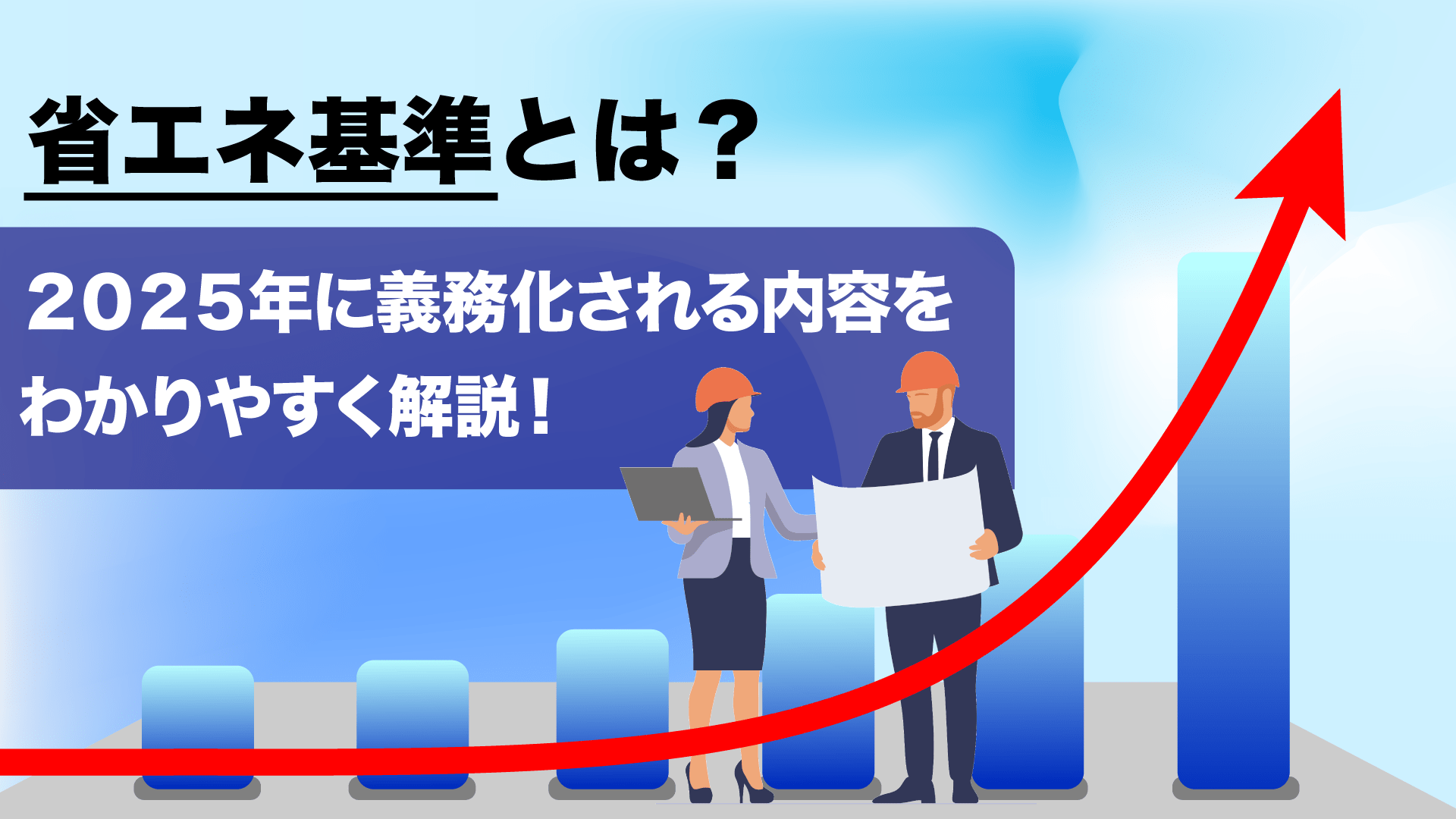
2025年4月から、建築物の省エネ基準適合が原則すべての建築物に義務化されることをご存じでしょうか。これまで届出や説明義務のみが求められていた小規模な住宅や建築物も、省エネ基準を満たさなければ着工・使用開始が遅延する可能性があります。適合性審査に不合格となり、工期が遅れるという事態は何としても避けたいところです。
そこで今回は、省エネ基準の基本的な考え方から、2025年の義務化で何が変わるのか、そして現場での対応策まで、建設業界で働く管理者や経営者の方に知っておいていただきたいポイントを徹底的に解説していきます。法改正へ迅速な対応は、企業のブランド価値向上や市場競争力の強化につながりますので、ぜひ参考にしてください。
省エネ基準とは?
省エネ基準とは、建築物省エネ法にもとづいた「建築物エネルギー消費性能基準」のことです。建築物が備えるべき省エネルギー性能を確保するため、建築物の構造や設備に関して守るべき技術的な指針を定めたものです。
この基準の対象は、個人の住宅からオフィスビルや商業施設といった非住宅建築物まで、すべての建築物に及びます。設計段階から施工、そして完成に至るまで、それぞれのプロセスでこの基準が適用されるイメージです。
省エネ基準を満たすことは、環境負荷を低減するだけでなく、光熱費の削減による顧客満足度の向上、さらには企業の技術力を示すことによる競争力の強化といった、事業面でも多くのメリットが期待できます。
なお、建築物省エネ法に関するより詳細な情報は、国土交通省の公式サイトで公開されていますので、一度ご覧になることをおすすめします。

省エネ基準が求められる理由とその背景
省エネ基準が定められた背景には、地球温暖化の進行やエネルギー資源の枯渇といった地球規模の課題があります。温室効果ガスの排出削減が国際的な急務となる中、建築分野におけるエネルギー消費の抑制が強く求められています。
特に化石燃料への依存を減らし、限られた資源の有効活用は、SDGs(持続可能な開発目標)の観点から重要です。
また、省エネ基準を満たした建築物は、冷暖房費や照明費といった日常的な光熱費の削減が可能となり、家庭や企業におけるコスト負担の軽減につながります。とりわけ企業にとっては、エネルギーコストの削減が経営効率の向上や競争力強化につながるので有益です。

より詳しい情報は、国土交通省の「建築物省エネ法の概要」資料に詳しく記載されています。
省エネ基準適合の判断基準
省エネ基準への適合は、「建物の断熱性能」と「設備機器のエネルギー効率」といった2つの評価軸で判断されます。住宅や非住宅建築には、それぞれの用途・規模に応じた基準値と評価指標が設定されており、客観的な評価によって判断される仕組みです。
ここで重要となるのが、「外皮性能」と「一次エネルギー消費性能」の2点です。
外皮性能:断熱性の重要な指標
外皮性能とは、住宅の外壁・屋根・床・天井・開口部などの熱的性能を数値化して評価する項目です。住宅においては、以下の2つの指標が用いられます。
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- ηAC値(冷房期平均日射取得率)

なお、非住宅建築物の場合は、ペリメータゾーン年間熱負荷係数など、建物用途に応じた別の評価指標を用いるのが一般的です。
一次エネルギー消費性能:建物の省エネを評価する指標
もうひとつの評価項目が、設置一次エネルギー消費性能です。以下の5つの設備カテゴリーのエネルギー消費量をもとに、その消費量を算出します。
- 暖房設備:使用する暖房方式や断熱性の高さによって消費量が変わる
- 冷房設備:冷房機器の種類や建物の遮熱性能によって消費量が変わる
- 換気システム:熱交換型換気や自然換気などによりエネルギー消費量が変わる
- 給湯機器:給湯器の種類(ガス、電気、ヒートポンプなど)を評価に反映
- 照明設備:照明方式や制御機能(人感センサー、調光機能など)が消費量に影響

省エネ基準を満たすために、一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量を下回る必要があります。なお、基準一次エネルギー消費量は、建物の構造や面積、設備仕様などに基づいて算定される個別の基準値であり、建物ごとに異なります。

2025年に義務化!省エネ基準の変更点
あらためて、今回義務化された省エネ基準の変更点を解説します。
- 原則すべての建築物が対象
延べ面積2,000平方メートル以下の新築建築物も対象 - 地域ごとに異なる外皮性能
建築物の外皮性能についても明確な基準が設置 - 一次エネルギー消費性能の基準値
すべての新築建築物に対して義務化 - 省エネ基準への適合性審査を実施
すべての新築建築物で審査手続きが必須
原則すべての建築物が対象
2025年4月から、省エネ基準の適合義務が大幅に拡大されます。従来は延べ面積2,000平方メートル以上の大規模建築物が対象でしたが、2025年からは延べ面積2,000平方メートル以下の住宅や非住宅建築物も含む、原則すべての新築建築物が対象となります。
小規模な建築物においても、従来は省エネ基準の「説明義務」にとどまっていましたが、今後は実際に基準を満たすことが法的に求められます。これにより、単に届出をすれば建築可能だった小規模建築物でも、省エネ性能を設計段階から確保しなければなりません。
この制度変更は、設計・施工プロセス全体の見直しを迫るものです。建築主や設計者、施工者は、改正内容を正確に理解し、計画段階から省エネ基準を遵守する体制を整える必要があります。
地域ごとに異なる外皮性能
省エネ基準の改正により、建築物の外皮性能についても、明確な基準が設けられるようになりました。特に断熱材や開口部(窓)などの性能は、設計段階から厳格にチェックされる項目となります。
外皮性能を評価する代表的な指標が、先述した「UA値(外皮平均熱貫流率)」です。これは建物全体からどれだけ熱が逃げやすいかを示す数値で、数値が小さいほど断熱性が高いことを意味します。2025年4月以降は、すべての新築建築物において、UA値を基準値以下に留めなければなりません。
なお、UA値の基準値は全国で一律ではありません。北海道などの寒冷地域では、より厳しい基準が設定されており、建物の断熱性能をさらに向上させる必要があります。気象条件に適した基準値を設けることで、過不足のない省エネ設計を推進することが狙いです。
一次エネルギー消費性能の基準値
建築物が使用するエネルギー全体を定量的に評価する一次エネルギー消費量基準の適合も、すべての新築建築物に対して義務付けられます。ここで用いられる指標が「BEI(Building Energy Index)」であり、その数値は1.0以下でなければなりません。
BEIとは、建築物が設計段階で使用すると見込まれる冷暖房・給湯・照明・換気などのエネルギー量を、基準となる標準的建物と比較するものです。仮にBEIが1.0を下回る場合、その建物は基準よりもエネルギー消費性能に優れていると評価されます。
BEIの改善には、高効率エアコンや給湯器、LED照明、太陽光発電といった省エネ設備の導入が効果的とされています。
ただし、2026年春には、延べ面積300平方メートル以上の非住宅建築物に対し、BEI基準が1.0から0.75〜0.85へと厳格化される予定です。さらには2030年、小規模建築物においてもBEI基準が0.8に強化されるなど、段階的な引き上げが決まっています。
省エネ基準への適合性審査を実施
2025年4月以降、すべての新築建築物について、省エネ基準を満たしているかどうかを確認する審査手続きが必須となります。建築主は申請書に加えて、建築物の設計図書や省エネルギー計算書などの詳細な書類を添付して提出します。
省エネ基準を満たさない建築物や、必要な手続きを怠った場合には、着工許可が下りません。そのため、建築工事の開始や、建物の使用開始が大幅に遅れ、顧客との契約破棄につながる恐れがあります。
また、従来に比べて申請書類の準備や、審査プロセスが複雑化しているため、建築主は制度内容を正確に理解し、適切な対応を取る必要があります。

2025年省エネ基準義務化への備え方と対応のポイント
省エネ基準義務化により、建築現場の負担増加は避けられないでしょう。そのため、以下のように現場との円滑な情報共有や遠隔臨場の導入が、対応のカギとなります。
- 省エネ技術導入にともなう現場管理の複雑化
断熱性能の向上や高効率設備の導入 - 現場負担軽減のための情報共有システム活用
遠隔臨場やデジタル技術の導入 - 2026年・2030年基準強化への長期的対応
今後さらに複雑化する省エネ要件に対応できるよう管理体制を整備
ここでは、省エネ基準義務化において備えるべきこと、そして対応のポイントを解説します。
省エネ技術導入にともなう現場管理の複雑化
省エネ基準への適合には、断熱性能の向上や高効率設備の導入が欠かせません。それにともない、設計段階からエネルギー消費量の計算や断熱材の選定など、従来以上に詳細な計画が必要です。
また、施工現場においては、断熱材の正確な施工や気密性確保などの重要度が上がります。基準を満たさない場合、確認済証が発行されず着工することができないため、設計から施工まで、一貫した品質管理が求められます。
現場負担軽減のための情報共有システム活用
現場の負担を抑えるためには、設計者・施工者・現場監督者のあいだで、円滑に情報を共有できる体制づくりが必要です。
たとえば、遠隔臨場技術を導入すれば、専門技術者が現場に常駐せずとも、リアルタイムで施工状況を確認し、的確な指導を行えます。さらに、デジタル技術を活用した現場コミュニケーションシステムを導入すれば、図面変更や施工指示の伝達がスムーズになり、複雑な基準要求を漏れなく、現場に反映できるでしょう。
遠隔臨場技術の導入は、現場管理におけるコスト削減や品質向上を実現します。遠隔臨場について詳しく知りたい方は、「遠隔臨場とは?注目されている背景や導入メリット、注意点を紹介」をご覧ください。
2026年・2030年基準強化への長期的対応
2025年の省エネ基準義務化は、始まりに過ぎません。すでに、その先の段階的な基準強化が決定しています。
具体的には、2026年には延べ床面積300平方メートル以上の非住宅建築物を対象とした基準強化が予定されており、2030年にはZEH(ゼロエネルギーハウス)水準の基準が新築住宅の標準となる見込みです。
こうした段階的な基準強化に対応していくには、今のうちから遠隔臨場システムやデジタル技術を活用した管理体制を整備しておくことが重要です。これにより、今後さらに複雑化する省エネ要件にもスムーズに対応できるようになります。
未来を見据え、遠隔臨場をはじめとしたデジタル技術の導入は、これからの建設業務運営において不可欠といえるでしょう。

現場との確実で円滑な情報共有なら「SynQ Remote」で!
2025年からの省エネ基準義務化により、建設業界は新たな段階に入ります。外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方で基準をクリアし、適合性審査を確実に通過するためには、適切な品質管理が欠かせません。
そこでおすすめなのが、現場管理特有の課題を解決するために設計された、現場特化型のビデオ通話ツール「SynQ Remote(シンクリモート)」です。
「SynQ Remote」は、遠隔地にいる管理者と現場作業者をリアルタイムで接続し、まるで横にいるかのように現場の確認・指示できるツールです。特別な機器や複雑な設定は不要で、普段使用しているPCやスマートフォンにアプリをインストールするだけで利用できます。
アカウント登録不要で社外の相手とも手軽に通話可能です。現場の「あれ、これ、それ」が正確に伝わるため、省エネ基準に関する細かな施工指示も確実に共有することができるでしょう。現場管理に悩んでいる管理者・経営者は、ぜひ一度「SynQ Remote」の導入をご検討ください。